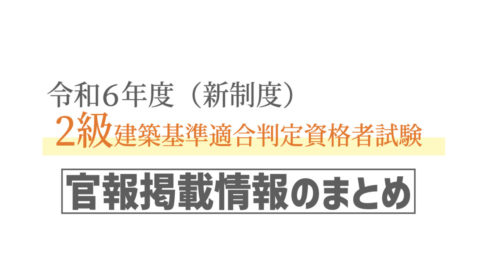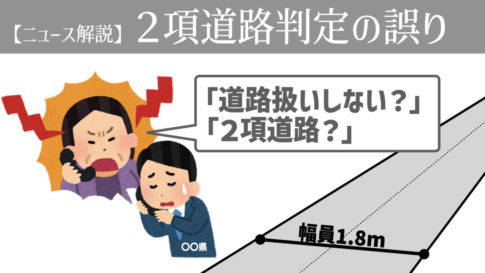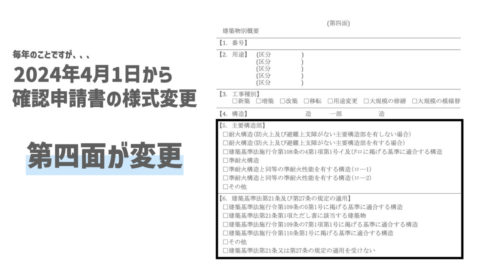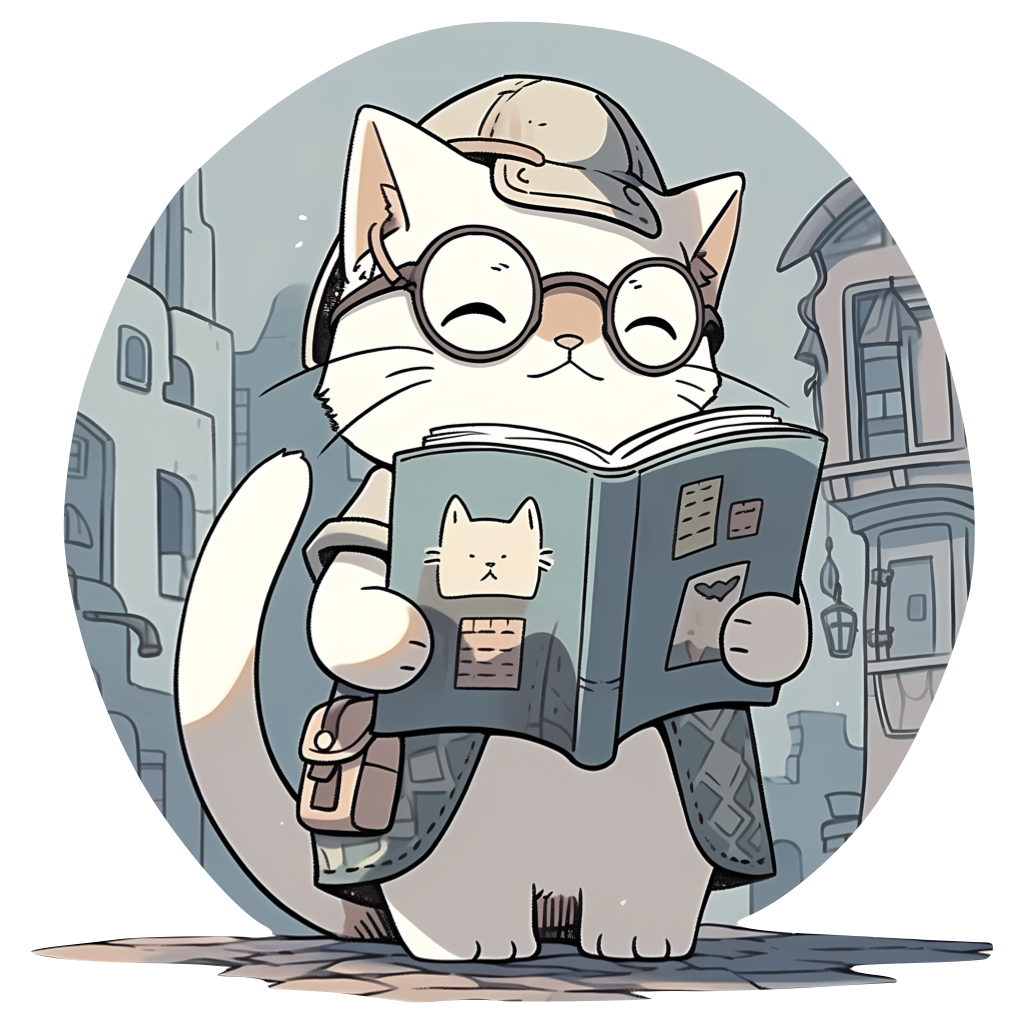太陽活動と都市について少し考えてみました。
何を言っているか分からないと思った方・・・寂しいですがスルーでもいいです。笑
少し興味が持ったなら是非読んでみてください。^^
目次
はじめに
これから(既に黒点が観測されなくなっているらしい)、太陽活動が低下する時期に突入するのではないかと、太陽と地球温暖化などの研究をされている研究者達から囁かれています。
知っている人はいるかもしれません。
江戸時代、マウンダー極小期という小氷期があったことは有名ですが、天明の飢饉があり、大きく人口が減少し、この時代に生きていた方はこの70年間はとても辛い思いをしたはずです。
※小氷期とは、1300年ごろから1850年ごろの約550年間続いた気候の寒冷化の時代のこと。
夏の平均気温が現在に比べて約0.5℃低いくらいだったので、あまりピンと来ないかもしれませんが、農作物の生産数の変化が当時の人にとってどれほど影響を与えていたかを考えてみると分かるかもしません。
現在でも、夏がちょっと寒かっただけで、作物の生産数が減り、農作物の価格に大きな影響を与えていますよね。
※この小氷期時代には、ウォルフ極小期(1280年から1340年ごろまで)、シュペーラー極小期(1420年から1570年ごろまで)、マウンダー極小期(1645から1715年ごろまで)という大きく3つの大きな寒冷時期があったようです。
それが、これから到来する可能性があると指摘されています。
太陽活動と気温の関係について
太陽活動が低下すること地球に侵入する宇宙線粒子量が増加することがわかっており、この宇宙線粒子量が雲の生成を促すことにより、日光の流入が減り気候が寒冷化すると考えられているようです。
ただ、温室効果ガスの影響により相殺されてしまうと考えている方もいるようですね。
過去の気温は、木などからの炭素量等から算出される推定で、現代の気温は気温計を使用しているので、都市部の気温を平均とした場合、高いのは当然ですから、温室効果ガスの影響ってどの程度あるのかは何とも言えないと私自身思っていますけど・・・。
都市部以外の平均気温を使用すればそんなに変わっていないんじゃないかな・・・
それでも、温室効果ガスを減らすのは現代の責務だと思いますけどね。
脱線しましたが、今回の本題は、この小氷期の到来についてです。
この小氷期の時代になると都市は大きく影響を受ける可能性が高い。
都市を活用する
現代でさえ、沖縄を除き、冬季は寒いし、ウイルス性の疾患にはかかるし・・・よくないことばかり、その中で、さらに平均気温が下がれば住みにくいことこの上ないですね。
まぁ、でも江戸時代はその小氷期を耐えてきたんですから、すごい・・・東北や北陸の方々は本当にすごいなと感心します。
現代は温かい住宅があるので、冬場はなんとかなりますが、当時の住宅技術では断熱性は皆無ですから、火鉢や囲炉裏などで寒さを凌いでいたんでしょう・・・
春の到来をどんなに待ちわびていたのか、もしかしたら寒い冬を逆に楽しんでいたかもしれませんね。
本題に戻り、これからこの寒い時期が到来したとすると、都市はどうすればいいのか。
私個人の見解ですが、都市の発展には、暑さも寒さも両方いらない、適度な気温が最適だと思うんですよね。
なかには、四季があるからこそ、いいんだと考える方もいるでしょう。
私も、春から夏への変わり目が一番好きですし、四季は好きなんですが、今回はちょっと視点が違います。
話を続けますが、時期によって、住む地域を変えるのが良いと思うんですよね。
例えば、夏場は北海道や長野の避暑地などの涼しい地域に移り、冬場は沖縄や全天候型の施設を備えた都市(つくれるか分かりませんが・・・笑)に移り住む。
ですので、個人は固定資産を極力持たない方がいいかもしれないんです。
固定資産を持つことによるメリットは、資産を次の世代(自分の子供や孫)に残すことができるということ。
けれどそれは、身動きが取れなくなってしまう要因でもあるということです。
キャッシュで買える人は別ですけど、多くの人はローンになりますよね。
多くの方が一度は『夢のマイホーム』を考えたことがあるでしょう。
私も建築士ですので、建てることには賛成です。
住宅市場が伸び悩んでいるなかで、こういう考えの方が増えるのは嬉しい限りです。
けれど、50年や100年先を考えると本当に正しいことなのかと考えてしまう。
自由に行き来できる生活スタイルの方が、『都市』が何かの要因により成立できなくなったとき、有利であると思うからです。
『都市』が成立しないって何だって思いますでしょ。
自然災害、事故、人口減少・・・etc などです。
これって、今、生きている人で気づいている人は本当に少ないと思います。
でも、東日本大震災のような災害はいつどこでも起きる可能性はあるんですよね。
ここまで移動を前提とした生活スタイルについて話してきましたが、これ以外にも小氷期を迎える上で解決する方法があるんです。それは交通です。
交通により都市間距離を短くする
交通の発展が生活スタイルを変える。
江戸時代は、馬が最速の乗り物でした。
ですが、庶民は馬が乗れない、歩きですよ。
つまり、日常生活の圏域は徒歩圏内に限られていた。
だから、その徒歩で動ける範囲でしか都市は発展して来なかったんですね。
それが、明治になり鉄道が発展したことにより、都市の距離感が縮まっていき、さらに車により、縮まっていった。
その交通による移動時間が都市の経済圏をつくっていったんですね。
注)厳密には、所得と交通料金の関係も大きく影響するので、必ずしも全ての都市で相関しない。
スーパー・メガリージョンって聞いたことありますか?
日本では国交省が取り組みを進めており、簡単にいうと、リニア中央新幹線の実現によって、東京と大阪間が約1時間で結ばれることで、約6,000万人の人口を持つ一つの大きな経済圏が成立することです。
国交省の検討会議はこちらをご覧ください。『スーパー・メガリージョン構造検討会』(外部リンク)
劇的にライフスタイルが変わることは間違いないですね。
なんと、名古屋と東京間は40分ですから、簡単に通勤できてしまう距離です。
これにより、『都市』は劇的に変わるんです。
都市の課題を解決し、成長するには高速で移動する機関が必要不可欠
つまり、都市間の経済距離を短くすることが一番重要ということです。
移動時間が短縮されることで、生活スタイルが劇的に変わります。
自身が東京の会社に勤めているとして、仙台から40分で通勤可能(仮に交通費の影響は無いとして)であれば、夏場が涼しい東北地方や長野の避暑地に住んでもいいかもなって考えませんか。
ここで、旅客機の可能性を指摘されそうですが、旅客機は音速に違い速度で飛行しているので、確かに早いですが、都市から空港までの距離とフライトまでの時間と着陸後から都市までの時間と輸送量を考慮すると、都市中心部への速達性と大量の輸送が可能な鉄道には敵わないと思います。
もう一つは、高速道路です。
高速道路は、自動運転技術の導入によって、非自動運転車を排除して、走行車両の安全性を向上させることで制限速度をあげて、都市間の距離を短縮させる動きに今後シフトいくことが重要じゃないかなと考えられます。
従来の都市圏の考え方は捨てた方が良い
ですので、自分の都市の発展ばかり考えていると、取り残される可能性があるかもしれません。
例えば大型店舗の出店で近隣都市と喧嘩している場合じゃなく、いち早く大きな経済圏を交通によって成立させるように取り組んでいった都市の方が経済的成長の機会は増加すると思います。
従来の考えで都市圏を考えていると都市はそれ以上発展しない。
特に地方都市は顕著だと思います。
リニア新幹線によって、東京ー名古屋の経済成長は進みますよ。
おそらくこの経済圏に吸収されてしまうかもしれない・・・笑
もっと俯瞰的に考えて都市同士が連携しないと、地方圏はまずい。
(県境・市町村界で都市を閉鎖的に見ている場合じゃない)
交通で1時間圏域で結ばれる都市同士は連携して、一つの都市をつくり上げることが大事じゃないかと、
そういった都市が100年後において生き残ることができる。
そうです、冷えていく地球の中で衰退するのではなく成長するためには、交通しか解決方法はない。
この交通は、日本国内においてまだまだ発展の余地があるということ。
交通の必要性を考えるときは連携都市の発展性を加味した費用便益分析を新たに設ければ整備の必要性は上がるし、また整備を促進させる方法として個人や民間企業による投資対象にする考えもありかと・・・
終わりに
小氷期と都市の関係性について記事にしてみましたが、支離滅裂の部分や主観的な部分もあり、少し読み難かったかもしれません。笑
ただ言いたかったのは、小氷期が到来するかもしれないということ、農作物(特に稲)は被害を受けるでしょうし、小氷期における江戸時代の過去の歴史から想像するに閉塞感が漂う時代になるかもしれない。
その様な中、閉塞感を無くし成長し続けるには『都市』が持続するしかないということ・・・
最後まで読んで頂きありがとうございました٩( ‘ω’ )و