こんにちは。建築士のやまけんです!!
今回は、標記タイトルでお送りします。
道路位置指定とは
道路位置指定(位置指定道路)とは、建築基準法第42条第1項第五号に位置付けられている道路のことで、基本的には都市計画法に基づく開発行為に該当しない土地造成(区域規模としては1,000㎡以内、首都圏や近畿圏だと500㎡以内)において築造される道路のことです。
開発行為に該当しない規模の宅地造成ですが、中には開発逃れのケースもあります。
開発行為によりも技術基準が劣る(開発こ行為においては都市計画法において技術基準が定められているが、建築基準法においては法第19条がメインとなる)ことから、逃れとして整備しているケースだと、法的にグレーゾーンなケースもあるので要注意です。
なお、「道路」なので道路法で築造されるものではないのか?と疑問に思うかもしれませんが、基準については、建築基準法において(厳密には政令)定められています。
[建築基準法第42条第1項(抜粋)]
この章の規定において「道路」とは、次の各号のいずれかに該当する幅員四メートル(特定行政庁がその地方の気候若しくは風土の特殊性又は土地の状況により必要と認めて都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内においては、六メートル。次項及び第三項において同じ。)以上のもの(地下におけるものを除く。)をいう。一〜四 (略)
五 土地を建築物の敷地として利用するため、道路法、都市計画法、土地区画整理法、都市再開発法、新都市基盤整備法、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法又は密集市街地整備法によらないで築造する政令で定める基準に適合する道で、これを築造しようとする者が特定行政庁からその位置の指定を受けたもの
それでは、解説していきましょう。
道路位置指定(位置指定道路)の基準
道路の基準は、建築基準法施行令第42条第1項第五号に定められていますが、道路の基準については、建築基準法施行令第144条の4第1項及び第2項に規定されています。
一号から五号まで具体的な基準が設けられており、次のようになっています。
| 各号 | 基準 |
|---|---|
| 一号 | 両端が他の道路に接続 ただし、次のイからホのいずれかに該当する場合には、袋路状道路(行き止まり道路)にすることが可能。☑️道路位置指定は基本的に行き止まりではなくて、道路(建築基準法上の道路)に接続しなさいというものです。ただし、袋路状道路でも良い場合があります。それが一号のイからホに掲げる基準のいずれかに該当する場合です。 |
| イ | 延長が35m以下 ※6m未満の袋路状道路(行き止まり道路)に接続する場合は、当該袋路状道路の延長を含む。☑️道路位置指定の端から端までの延長(基本的には道路中心線の延長)は35m以下にしなさいというものです。なお、幅員6m未満袋路状道路に接続する道路位置指定の場合には、袋路状道路の始点からの距離が35m以下にしないとするものです。 |
| ロ | 終端が公園、広場等の自動車の転回に支障がない☑️特定行政庁ごとに取り扱いを定めていますが、基本的には自動車の転回が可能な空地等(空地等を永久的に利用できる担保等が必要)が必要となるようです。 |
| ハ | 延長が35m超えで、終端と35m以内ごとに転回広場 *転回広場は、小型四輪自動車が2台以上停車することができること(昭和45年建設省告示第1837号) *小型四輪自動車が転回できる形状であること☑️道路位置指定の延長が35mを超える場合及び道路の終端には、転回広場(横浜市ですと、2m以上の隅切り、道路幅員以上の幅、及び延長は5m以上など)を設けなさいとするものです。 |
| 二 | 幅員が6m以上☑️道路幅員が6m以上あれば、袋路状道路でもOKです。 |
| ホ | イから二に準じる場合で特定行政庁が周囲の状況により避難及び通行の安全上支障がないと認めた場合☑️やむを得ない場合の例ですが、特定行政庁ごとに取り扱いがあります。 |
| 二号 | 道路交差部は、2m以上の隅切りを設ける *特定行政庁が周囲の状況により避難及び通行の安全上支障がないと認めた場合は、隅切りを設けてなくても良い。☑️交差点は隅切りがないと、左右から車を視認することができないでしょう。そのため、隅切りを設けるよう規定されています。なお、設けなくても良い例としては、幅員の広い歩道がある場合や、交差点の内角が120度以上の場合などです。 |
| 三号 | 砂利敷その他ぬかるみとならない構造☑️現代で砂利敷にするところは少ないとは思いますが、基本的にはアスファルト舗装が一般的ですかね。特定行政庁によっては、道路構造の基準を定めているケースが多いので道路構造には留意しましょう。 |
| 四号 | 縦断勾配は12%以下かつ階段状ではないこと *特定行政庁が周囲の状況により避難及び通行の安全上支障がないと認めた場合には、これによらなくても良い。☑️12%勾配というのは、10m進むと1.2m上がる計算です。勾配としては、かなりキツめなので、極力避けるべきですね。なお、特定行政庁によっては、滑り止めをするなどの対策を指導するところもあります。 |
| 五号 | 側溝、街渠等を設ける☑️道路雨水を流すための側溝や街渠を設けないとするものです。一般的な道路をイメージしてもらえればいいかなと思います。 |
なお、条例で政令と異なる基準を定めることができるとされています。(基準を緩和する場合には、国土交通大臣の承認が必要)
横浜市や福岡市の例が分かりやすいので、参考にしてみてください。
▶️横浜市(道路位置指定に関するページへのリンク)
▶️福岡市(道路位置指定に関するページへのリンク)
では、次に、申請に必要な書類等などについて解説します。
申請に必要な書類など
法律で定められている書類等は次のようになっています。
①申請書
申請書は正副2通に②及び③を添付
②図面
| 図面の種類 | 明示すべき事項 |
|---|---|
| 附近見取図 | 方位、道路及び目標となる地物 |
| 地籍図 | 縮尺、方位、指定を受けようとする道路の位置、延長及び幅員、土地の境界、地番、地目、土地の所有者及びその土地又はその土地にある建築物若しくは工作物に関して権利を有する者の氏名、土地内にある建築物、工作物、道路及び水路の位置並びに土地の高低その他形上特記すべき事項 |
③承諾書
道路の敷地となる土地の所有者
道路の敷地となる土地にある建築物・工作物に関して権利を有する者
道路の基準(建築基準法施行令第144条の4第1項及び第2項)に適合するよう管理する者
④その他必要な書類は、特定行政庁が定めている
補足
道路位置指定(位置指定道路)については、特定行政庁ごとに取り扱いを定めており、設計にあたっては、特定行政庁の取り扱いの確認は必須です。
また、必要な書類についても、公図をはじめとして、必要なものを定めていますので、必ず確認が必要です。
その取り扱いの中で、審査に係る期間や公告までのスケジュールなどを示している例が多いですので、必ず確認した上で、道路位置指定を受ける特定行政庁と打ち合わせを行いましょう。
道路位置指定に接道する土地の購入時の注意点
道路位置指定は、ほぼ間違いなく『私道』です。
私道ですと、私権が複雑に絡みます。といっても、道路の維持管理に関する取り決めを利用者の協定により確実に定めることで無用なトラブルを回避することができます。
道路位置指定に接道する土地を購入すること自体は問題ありませんが、そのための条件として、利用に関する協定や利用に関する費用負担(←金の取り決めがあることが最も大切)の取り決めがされてることが必須だと考えます。
関連記事を貼っておきます。
それでは、簡単ではありますが、今回はここで終わります。
タイトル写真)
PexelsによるPixabayからの画像


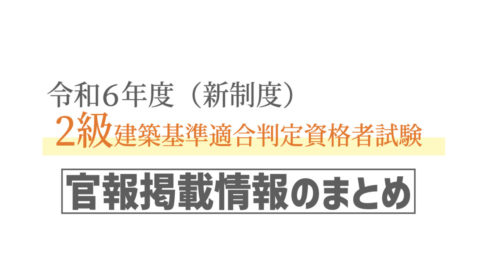
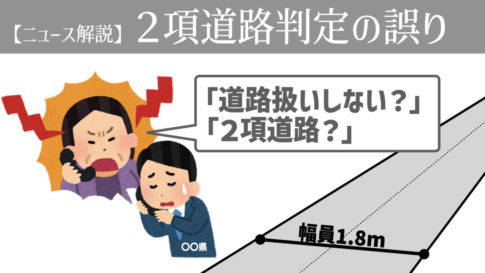
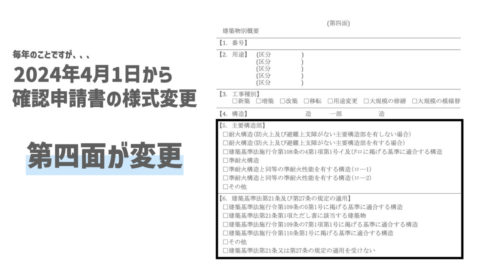


・道路位置指定の構造的な基準とは?
・道路位置指定に接道する土地を購入する際の留意点とは?