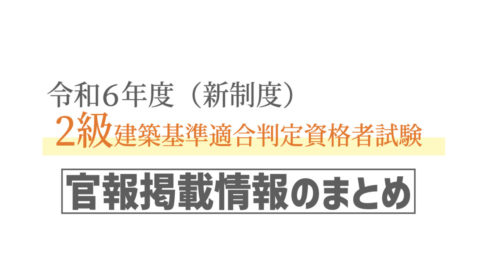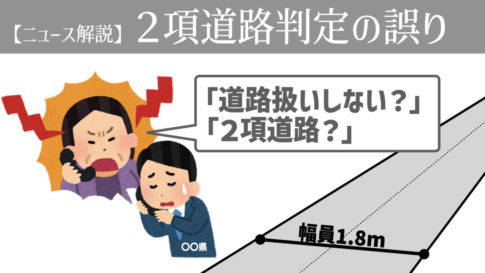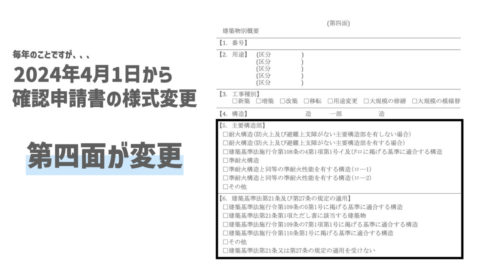この記事では、都市計画法で定められる工業系用途地域(工業地域、工業専用地域。*準工業地域を除く)内の用途制限を解説しています。
どういった用途の建築物の建築することが可能なのか解説しています。
こんにちは!!やまけんといいます^ ^
やまけんブログでは、建築や都市計画、不動産に関して業務に役立つ豆知識を発信しています。
工業地域の目的と建築制限一覧
工業地域は、都市計画法において、「主として工業の利便を増進するため定める地域」とされています。
工業地域は、環境を悪化させるおそれがある工場や危険物の貯蔵・処理の量が多い施設の立地が可能となっており、工業専用地域と並んで”工業”のための用途地域となっています。
建築制限は、建築基準法第48条第12項、別表第2において定められており、まとめて表にすると次のようになります。
| 号 | 建築物の用途 | 備考 |
|---|---|---|
| 一 | ・個室付浴場業に係る公衆浴場 ・ヌードスタジオ ・のぞき劇場 ・ストリップ劇場 ・専ら異性を同伴する客の休憩の用に供する施設 ・専ら性的好奇心をそそる写真その他の物品の販売を目的とする店舗 ・その他、上記に類するもの。 | ・(る)項第三号 *施行令第130条の9の5 |
| 二 | ・ホテル ・旅館 | |
| 三 | ・キャバレー ・料理店 ・上記に類するもの | *料理店:食堂やレストランなどではなく風俗営業法に規定する料理店 |
| 四 | ・劇場 ・映画館 ・演芸場 ・観覧場 ・ナイトクラブ ・客にダンスをさせ、かつ、客に飲食をさせる営業(客の接待をするものを除く。)を営む施設(ナイトクラブを除く。) | *施行令第130条の7の3 |
| 五 | ・学校 | *幼保連携型認定こども園を除く |
| 六 | ・病院 | |
| 七 | 下記用途で床面積が1万㎡を超えるもの ・店舗 ・飲食店 ・展示場 ・遊技場 ・勝馬投票券発売所 ・場外車券売場 ・場外勝舟投票券発売所 | *施行令第130条の8の2 |
工業専用地域の目的と建築制限一覧
工業専用地域は、都市計画法において、「工業の利便を増進するため定める地域」とされています。工業地域との違いは、最初の”主として”が無いだけです。
つまり、工業の利便増進に関わる建築物以外は建築することができません。
そのため、建築基準法において制限する建築物の用途もそのようになっており、住居系の建築物の建築ができないといった規定となっています。
建築制限は、建築基準法第48条第13項、別表第2において定められており、まとめて表にすると、次のようになります。
| 号 | 建築物の用途 | 備考 |
|---|---|---|
| 一 | ・工業地域内で建築してはならない建築物 | ・(を)項 |
| 二 | ・住宅 | |
| 三 | ・共同住宅 ・寄宿舎 ・下宿 | |
| 四 | ・老人ホーム ・福祉ホーム ・上記に類する用途 | |
| 五 | ・物品販売業を営む店舗 ・飲食店 | |
| 六 | ・図書館 ・博物館 ・上記に類する用途 | |
| 七 | ・ボーリング場 ・スケート場 ・水泳場 ・スキー場 ・ゴルフ練習場 ・バッティング練習場 | *令第130条の6の2 |
| 八 | ・マージャン屋 ・ぱちんこ屋 ・射的場 ・勝馬投票券発売所 ・場外車券売場 ・上記に類する用途 |
補足:工業専用地域内では保育所は建築できるの?
結論から言うと、保育所は、建築することが可能です。
根拠としては、国土交通省が発出している技術的助言によります。(平成5年時点は通達)
(根拠)
「都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律等の施行について(平成5年住指発第225号)」により、次のように書かれています。抜粋版
第四 用途地域について
「〜(略)〜保育所等については、工場勤務者等に必要不可欠な通園施設であり、工業専用地域内でも建築が可能であることに留意されたい。
まとめ
今回、記事にしていない準工業地域については、危険物系の製造・貯蔵等を行う建築物や風営法の適用がある建築物は建築することができない規定になっていますが、それら以外は建築することが可能です(用途規制の中で一番緩いです)
今回の記事の注意点としては、建築する建築物の用途が工業系用途地域でも建築できるかどうかの最終判断は、特定行政庁や建築主事になってくるので、建物内の使い方で疑問がある場合(例えば、寮のような使い方の部屋があるなど・・・)は、ちゃんと建築計画を起こす前に、建築する土地を所管する行政に確認するようにしましょう。
今回は、ここまでとなります。
お読み頂きありがとうございました。٩( ‘ω’ )و