この記事では、指定確認検査機関の役割と特定行政庁との関係性について解説します。役割と関係性を知ることによって建築に関わる様々なプロセスをより理解しやすくなります。
また、建築主さん向けとしまして、建築士から建築確認申請の申請先について説明を受けたものの、十分に理解できなかった方の参考になればと思って執筆しています。
それでは、指定確認検査機関の役割と特定行政庁との関係性について解説していきましょう。
こんにちは!YamakenBlogへようこそ!
YamakenBlogでは、建築基準法や都市計画法、宅建業法など、まちづくりに関連する難解な法律を、元行政職員の私が分かりやすく解説しています。
このブログは、建築・不動産業界のプロから、家づくりを計画中の方、店舗立地を検討している方まで、誰でも役立つ情報が満載です!
ぜひ、ブックマーク登録を行い、今後も役立つ情報を受け取ろう!
*このサイトリンクはブログやメール、社内掲示板などで自由に使っていただいて大丈夫です!お気軽にどうぞ!
目次
指定確認検査機関の役割
建築着工の大半が占める住宅建築の場合ですと若年層の方々が多いです。ですので現在では一般的となった民間の指定確認検査機関を理解している方もいると思いますが、親御世代の認識であれば確認申請や完了検査を行うのは『役所でしょ?』という考えが普通かなと思います。
その役所が従来から行なっている建築確認審査や完了検査などを担うのが指定確認検査機関です。
少し詳しく説明しますと、平成13年(1999年5月1日改正法施行)の建築基準法改正によりこれまで行政が行ってきた建築確認審査や完了検査などを行う機関として新たに建築基準法に規定されたものです。
公務員と会社員で立場は違えど、行っている建築確認業務は同じです。
『行政は審査が遅いし電子申請や郵送申請では対応してくれないし、それに威圧的な態度が嫌い(←今はどうか分からないけど、建築という狭いコミュニティだとどうしても生まれてしまう)』
と思っている建築士の方は民間審査機関に出しているのではないかと思います。
それから民間審査機関に提出している理由として、資本関係からお付き合いもあるんじゃないかと思います。
指定確認検査機関は、行政と異なり売上がないと倒産してしまうのでサービス向上は重要ですから、行政よりサービスが良いです。(なお、地方の三セク機関では、建築行政職の再就職先なのでサービスに欠ける行政マインドの人が一定数います。笑)
結局はあの人がいるから、この審査機関に提出しようとかなと考えている建築士さんも多いはずです。
ではでは次に特定行政庁と指定確認検査機関との関係について簡単に説明していきます。
特定行政庁と指定確認検査機関との関係
特定行政庁は指定確認検査機関に対して指導や基準等のルールを正確に伝える立場にあります。
そのうち、なんといっても大事なのは指定確認検査機関が円滑に業務を行えるよう、建築確認審査に必要な法令解釈、自治体の条例、自治体独自のルールなどを指定確認検査機関に情報提供をすること。
このことを正確に伝えないと、行政が内規と称して建築設計に必要なルールをどこにも情報を公開しなければ、設計者も指定確認検査機関もそれに対応することができないんですよね。特に、相談しないと教えないとする特定行政庁も一定数あるのは注意です。
(わたしが在籍していた特定行政庁でも内規を有していました。当時は内規の公開・非公開について議論したことはなかったのですが、今思えば公開しないのであればルールとして定めてはいけないのでは後悔しています。)
このため、特定行政庁は指定確認検査機関に対して情報提供を行うことが重要かなと思います。
補足:指定確認検査機関→特定行政庁
指定確認検査機関は建築確認審査等を行った場合は次のようなルールが定められています。
- 指定確認検査機関は建築基準法第6条の2第5項の規定により建築確認済証を交付を行った場合には、交付後7日以内に確認審査報告書を特定行政庁に提出する
- 報告書類として、建築確認申請書の第4面から第6面(棟別の建築概要)と建築計画概要書等を提出することになります。完了検査や中間検査も検査済証の交付の日から7日以内と規定
なお、法第6条の2第6項では、特定行政庁は指定確認検査機関から報告を受けた建築計画が建築基準関係規定に適合しないと判断する場合には、特定行政庁の権限により失効させることが可能となっています。
これが課題なんですけど、指定確認検査機関から提出される確認審査報告書では図面や構造計算書が添付されていませんので、集団規定の一部くらいしかチェックできないのが実情かと思います。
ですので、この6項規定は難易度高いです。
実際、わたしが特定行政庁において確認審査を行っていた際の経験として、膨大な確認審査報告書のチェックは記載内容の申請書の誤記が中心となり結論的には法律に適合しているケースが多かったかなとと思います。ただし、ごく稀に道路に関して意味不明な記述をしていたり都市計画道路を見逃していたりと、、、(汗)
それでは最後に確認申請先はどう選択すればいいのかわたしの考えをお伝えしていきます。
確認申請先はどのように選択すればいいの?
確認申請先ですが、結論からいうと、行政・指定確認検査機関のどちらでもOKです。
建築主の方で申請先は自分で決めると考えている方を除いては建築士に任せましょう。
建築主の中にはどうしても役所がいい!と考えている方もいますが、審査においてチェックされる内容はどこでも同じです。
役所との違いは審査スピードや全国どこでも対応していること、電子申請に対応していることなどくらいです。民間のため行政よりも指定確認検査機関の方が審査手数料が高い傾向にあります。
ですので、繰り返しですが基本的には、建築士が申請しやすいと考えている機関に申請するのが一番かなと思いますから、建築主の方はあまり気にしなくてもが大丈夫です。
参考情報として統計的な側面と審査料金について簡単に説明します。
補足:統計的に確認申請提出件数が多い機関は?
はじめに全国的な統計をみてください。
確認申請情報(国公表)では次のようになっています。
| 合計 | 特定行政庁 | 特定行政庁の割合 | 指定確認検査機関 | 指定確認検査機関の割合 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全国総数 | 131,468件 | 11,527件 | 8.8% | 119,941件 | 91.2% | R1.10〜12 |
指定確認検査機関の割合が9割を超えています。
つまり、ほぼ指定確認検査機関に申請書を提出していることがわかります。理由はとしては次の2つかなと思います(あくまでも個人的な見解)。
- 審査期間が短い
- 電子・郵送申請に対応している
申請先の多くが指定確認検査機関となっているのは、建築主や建築士のニーズを抑えているのは違いありません。
とはいえ、先ほどもお伝えしましたが、大人の事情で申請先を固定しているケースもあるので、一概にいえない場合もあります。
また、申請先の料金が安いからと言う理由で決めてはなりません。特に特定行政庁の場合には、建築確認審査以外にも建築行政・まちづくりや建築物の違反指導、さらには宅地防災など、業務は多岐にわたっています。
そのため、審査期間が法定の期間(基本的には、住宅など小規模の場合は7日、それ以外は35日)程度となるのが一般的(これに申請内容に不備がある場合は修正や追加説明などに必要な期間が加えられる)ですから、審査期間の重視の場合には、申請料金だけで決めてはいけません。
では、次に申請代金をみてみます。
補足:確認申請料の比較
確認申請機関によって料金は異なります。住宅建築で多い床面積100㎡〜200㎡以内で比較してみます(東京都、横浜市、大手の民間機関)
| 床面積 | 東京都 | 横浜市 | 日本ERI | 住宅性能評価センター |
|---|---|---|---|---|
| 100㎡超え220㎡以内 | 14,000円 | 28,000円 | 55,000円 | 26,000円 |
みてもらうと分かりますが、特定行政庁(建築主事を置く市町村)や指定確認検査機関によってまちまちです。なお、特定行政庁(建築主事を置く市町村)の場合には特定行政庁の区域でしか審査を行うことができません。
指定確認検査機関の場合は、指定を受けた範囲で業務を行うことができますので、全国の地域で対応している機関もあります。
本記事のまとめ
この記事では次の3点について説明しました。
- 指定確認検査機関の役割とは?
- 特定行政庁と指定確認検査機関との関係とは?
- 建築確認申請先は選択することができるの?
指定確認検査機関の役割は、行政が担っている建築確認申請等の業務を行うことにあります。指定確認検査機関も行政も、建築確認や中間検査、完了検査などの審査を行う業務内容はどちらも同じです。
特定行政庁は指定確認検査機関を指導・監督する立場にあり、また、指定確認検査機関による建築確認審査が円滑にできるよう建築確認審査に必要な情報を提供する立場でもあります。
どちらの機関でも、建築物が建築基準法等の関係法令に適合しているかどうかを確認できますので、建築士が申請しやすい(審査機関の担当者が親切など)方を選択するのが結果的により良い建築物を建築できることにつながるかと思います。
ということで以上となります。参考となれば幸いです。

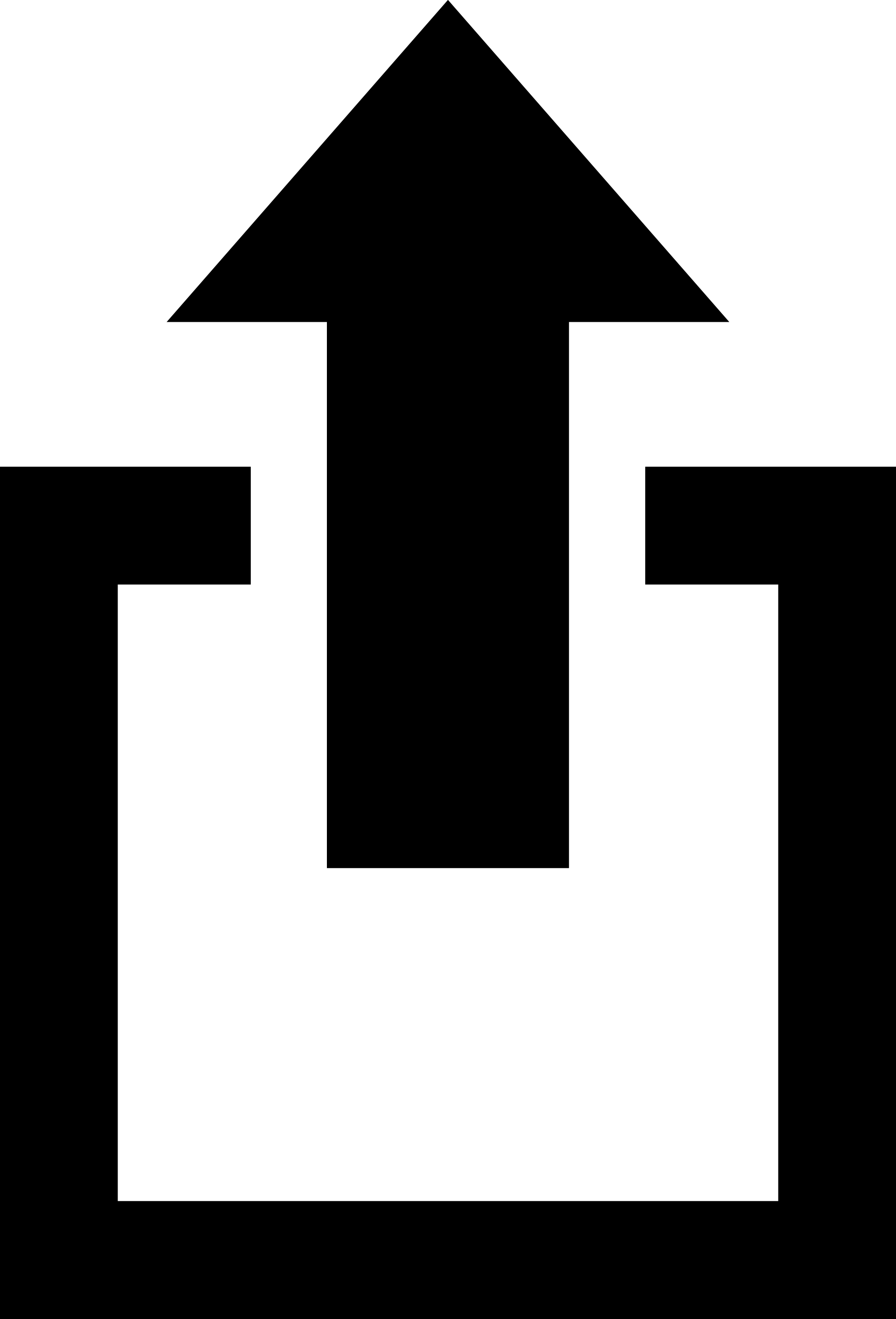 共有アイコンをタップし、「ホーム画面に追加」を選択してください。
共有アイコンをタップし、「ホーム画面に追加」を選択してください。



