この記事では、令和5年7月28日に閣議決定された「第三次国土形成計画(旧全総計画)」と「第6次国土利用計画」について、策定された背景やどういった方針でどのような施策が展開されようとしているのか、都市政策の観点から分かりやすく解説を行っています。
なお、はじめに「国土形成計画」と「国土利用計画」の違いについて知りたい方ははじめにこちらの記事をご覧ください。
関連記事
策定日は2023年7月28日
「第三次国土形成計画(旧全総計画時代から通算して第8次計画)」並びに「第6次国土利用計画」が策定されたのは、2023年7月28日となります。
両計画は、第二次岸田内閣時に閣議決定されました。
国土形成計画については、2050年先を見据えた新しい国土の姿として、「新時代に地域力をつなぐ国土」、国土構造の基本構想として「シームレスな拠点連携型国土」を設定しています。
一方で、国土形成計画と合わせて策定される国土利用計画については、計画の基本方針として、「持続可能で自然と共生した国土利用・管理」を掲げています。
・持続可能で自然と共生した国土利用・管理
続いて、国土形成計画並びに国土利用計画の概要について解説していきます。
第三次国土形成計画とは
国にてまとめた概要資料はこちら。

新たな国土形成計画は、2050年を見据えつつ、今後概ね10年間の国土づくりの方向性を定めています。
計画では、人口減少等の加速による地方都市の危機的状況や、巨大災害リスクの切迫、気候危機、日本を取り巻く国際情勢など、様々な危機・難局を乗り換えて、未来に希望を持てる国土の将来ビジョンを掲げることとしています。
掲げられている課題のポイントとしては、2008年の時点で約4.5人に1人が高齢者という状況が、2050年には約2.7人に1人というより深刻な状況となることに加えて、全国の約半数の地域(=地方)で人口が半減することが想定されていることなどが挙げられています。
一方で、コロナ禍以降、場所に縛られない暮らし方や働き方に加え、地方移住への関心の高まりも今後の国土形成において重要なワードの一つとして取り上げられているのが特徴です。
また、巨大災害リスクについては、今後30年以内の巨大地震の発生確率は70〜80%という状況(今後、さらに上昇)、近年の気候変動を受けて、短時間強雨(50㎜/h)の発生頻度は約1.4倍に増加している状況もあります。
これらに加えて、国際競争力の低下やエネルギー・食糧の海外依存リスクなどがあります。
国が直面するリスクと構造的な変化として、次の3つが示されています。
- 地域の持続性、安全・安心を脅かすリスクの高まり
- コロナ禍を経た暮らし方・働き方の変化
- 激動する世界の中での日本の立ち位置の変化
続いて、日本が直面するリスクと構造的な変化を踏まえ国土づくりの目標を「新時代に地域力をつなぐ国土〜列島を支える新たな地域マネジメントの構築〜」とし、基本的方向性を3つ示しています。
- デジタルとリアルの融合による活力ある国土づくり
〜地域への誇りと愛着に根差した地域価値の向上〜 - 巨大災害、気候危機、緊迫化する国際情勢に多応する安全・安心な国土づくり
〜災害等に屈しないしなやかで強い国土〜 - 世界に誇る美しい自然と多彩な文化を育む個性豊かな国土づくり
〜森の国、海の国、文化の国〜
続いて、基本的方向性を踏まえた国土づくりの戦略的視点として4つ示し、国土の刷新に向けた重点テーマがいくつか設定されています。
シームレスな拠点連携型国土
- 民の力を最大限発揮する官民連携
- デジタルの徹底活用
- 生活者・利用者の利便の最適化
- 縦割りの打破(分野の垣根を越える横串の発想)
- 地域生活圏の形成
・1時間圏10万人程度以上
・全国どこでも誰もが便利で快適に暮らせる社会 - 持続可能な産業の構造転換
・地域の特徴を活かした成長産業の全国的な分散立地等の促進
・GXや巨大災害リスク対応に向けた既存コンビナート等の基幹産業拠点の強化再生 - グリーン国土の創造
・30by30による健全な生態系の保全・再生の促進
・カーボンニュートラルの実現を図る地域づくり - 人口減少下の国土利用・管理
・持続可能な国土と地域の形成に資する最適利用管理
・安全安心な国土利用管理 - 国土基盤の高質化
・国土基盤の高質化に向けた戦略的マネジメントの徹底 - 地域を支える人材の確保・育成
・包摂社会に向けた地域づくりへの多様な主体の参加と連携
*包摂社会:全ての人々を排除せず、包摂し、共に生きることができる社会を目指す考え方
・民間の力を最大限活かした新しい公共の領域拡大
第三次国土形成計画は、現代の日本が抱えている課題を国土の土地利用の面から解決する方向性を示しています。いずれも早急に解決していく必要がある課題となっていますが、とりわけ重要なワードに感じられたのは次のものです。
❶東京一極集中の是正(デジタルの徹底活用、二地域居住の推進を含む)
❷リニア中央新幹線による超大都市圏の構成
❸成長産業(半導体、蓄電池等)のための工場用地確保
❹ネットワーク型コンパクトシティの形成(災害リスク低減、再エネ、地方消滅回避)
現時点では、人口減少と少子高齢化を劇的に改善する施策はないのが実情です。このため、国としては、少子化対策は継続実施していくものの、少子化は止められないものとして土地利用を行っていく姿勢に感じられます。
特にリニア中央新幹線により三大都市圏を1時間圏域の都市圏(人口:約7,300万人)とすることで、その効果を地方へ波及(東京一極集中の是正を含む)させたい考えが全面に出ているような印象を受けます。

都市政策の面でみると、2050年の人口半減市町村でも暮らしていけるよう概ね1時間圏域の人口を10万人程度以上とする地域生活圏の考えも示されています。
日常の暮らしが維持できるレベルということで従来は30万人が目安だったと記憶していますが、今回の国土形成計画から最低限の維持レベルとして10万人以上の都市圏となり、なおかつ、ドローンや自動運転、地域交通、遠隔医療やオンライン教育等を活用して全国どこでも便利で快適に暮らせる社会を実現しようとする考えにシフトしています。
とはいえ、現時点で1時間圏域で概ね10万人以上が確保できていない都市圏があるのも現状です。このため、おそらくは立地適正化計画(ネットワーク型コンパクトテシティ形成)の推進や災害リスク低減、災害からの早期復興などを踏まえて、より俯瞰的に安全な地域に居住を誘導していくのではと思います。
それにしてもリニア中央新幹線への期待は相当大きいです。確かに東京一極集中の解決の一としてリニア中央新幹線が果たす役割は大きいです。三大都市圏居住者にとっては大きなメリットです。同時に超大都市圏へ人口が集積する可能性もあり、一部の地域では巨大地震・津波による影響が大きい可能性があるのは留意しておきたい点です。
第六次国土利用計画とは
国にてまとめた概要資料はこちら。

はじめに国土利用計画を策定するにあたっての国土利用における基本的条件の変化と課題です。3つが設定されています。これらについて、デジタルを徹底活用した官民連携による地域課題の解決が示されています。
- 人口減少・高齢者等を背景とした国土の管理水準の変化と地域社会の衰退
・市街地の人口密度低下や中心市街地の空洞化
・所有者不明土地等の低未利用土地や空家等の増加
・土地利用効率の低下や管理水準の低下 など - 大規模自然災害に対する脆弱性の解消と危機への対応
・国土利用上、災害に対して脆弱な構想
・地球温暖化等の気候変動の影響
・巨大地震や津波による広域にわたる甚大な被害が発生する可能性 - 自然環境や景観等の悪化と新たな目標(カーボンニュートラル、30by30等)実現に向けた対応
・再エネ導入促進が求められている状況
・ネイチャーポジティブ(自然再興)の考えに根差した国土利用・管理
・里地及び里山の減少
*30by30:30by30(サーティ・バイ・サーティ)とは、2030年までに生物多様性の損失を食い止め、回復させる(ネイチャーポジティブ)というゴールに向け、2030年までに陸と海の30%以上を健全な生態系として効果的に保全しようとする目標
続いて、課題を踏まえた国土利用計画の全体的な基本方針として「持続可能で自然と共生した国土利用・管理」を掲げて、次の5つの基本方針を定めています。
- 地域全体の利益を実現する最適な国土利用・管理
・土地の利用・管理手法を定める地域管理構想の全国展開
・所有者不明土地や空き地の利用の円滑化、適正な管理
・荒廃農地の発止防止、利用
・地域の持続性確保につながる産業集積のための土地利用転換など
・重要土地等調査法に基づく調査等 - 土地本来の災害リスクを踏まえた賢い国土利用・管理
・気候変動に伴う水災害の激甚化・頻発化に対応する流域治水の推進
・災害ハザードエリアにおける開発抑制と居住誘導
・水源涵養等に重要な役割を果たす森林の整備、保全
・事前防災・事前復興の観点からの地域づくり - 健全な生態系の確保によりつながる国土利用・管理
・保護地域の拡充、OECMの設定・管理促進による広域的な生態系ネットワーク形成
・グリーンインフラ、Eco-DRRなど自然環境が有する多様な機能な活用した地域課題の解決
*Ecosystem-based Disaster Risk Reduction:生態系を活用した防災・減災
・カーボンニュートラルの実現に向けた地域共生型の再生可能エネルギー関連施設の立地誘導 - 国土利用・管理DX
・地域空間情報等のデジタルデータ、リモートセンシング等のデジタル技術の徹底活用による国土利用・管理の効率化・高度化
・効率的・効果的な国土管理を実現するため、各主体が所有するデータのオープン化、連携促進 - 多様な主体の参加と官民連携による国土利用・管理
・適切な利用・管理が行われていない土地の公共的管理の促進、利用拡大に向けた民の力の最大限の活用など官民連携の推進
・多様な主体の参加や連携を促進するコーディネート機能の確保
続いて、基本方針を踏まえて、地域類型別(都市、農村漁村、自然維持地域)及び利用区分別(農地、森林、原野等、水面・河川・水路、道路、住宅地、工業地、その他の宅地、その他(公用・公共用施設の用地・低未利用土地等)、沿岸域)の基本方向を定めています。
続いて、利用目的に応じた区分ごとの規模の目標が決められています。計画基準年次は2020年とされ、目標年次は2033年としています。なお、2033年の人口は1億1,800万人(三大都市圏:6,300万人、地方圏:5,400万人)、世帯数は5,300万世帯としています。
| 区分 | 2020年 (万ha) | 2033年 (万ha) | 2033年 構成比(%) |
|---|---|---|---|
| 農地 | 437 | 414 | 11.0 |
| 森林 | 2,503 | 2,510 | 66.4 |
| 原野等 | 31 | 31 | 0.8 |
| 水面・河川・水路 | 135 | 135 | 3.6 |
| 道路 | 142 | 147 | 3.9 |
| 宅地 | 197 | 198 | 5.2 |
| 住宅地 | 120 | 119 | 3.2 |
| 工業用地 | 16 | 17 | 0.5 |
| その他の宅地 | 61 | 61 | 1.6 |
| その他 | 334 | 344 | 9.1 |
| 合計 | 3,780 | 3,780 | 100.0 |
最も増減が大きいのが「農地」で、437万haから414万ha(▲23万ha)、続いて、「その他(公用・公共用施設の用地・低未利用土地等)」が334万haから344万ha(+10万ha)となっている。他に増減するのは道路(+5万ha)、工業用地(+1万ha)、宅地(+1万ha)となっている。
最後に、利用目的に応じた区分ごとの規模の目標を達成するための必要な措置として8つ定めされています。
- 土地医療関連法制等の適切な運用
- 土地の有効利用・転換の適正化
- 国土の保全と安全性の確保
- 自然環境の保全・再生・活用と生物多様性の確保
- 持続可能な国土管理
- 多様な主体による国土利用・管理の推進
- 国土に関する調査の推進
- 計画の効果的な推進
国土利用における必要な措置の概要としては、災害抑制(グリーンインフラの活用)、産業集積の促進を図る土地利用転換、災害リスクの低い地域への誘導、再エネ導入、ネットワーク型コンパクトシティの形成、市町村計画の全国展開などが予定されています。
特に、Eco-DRR(Ecosystem-based Disaster Risk Reduction)や30by30という考えが新たに示されています。Eco-DRRとは、土地の生き物や環境を保護して、自然の持つ力によって災害による被害を防止又は軽減させる取り組みや考え方のことです。
第6次国土利用計画では、国土形成計画と同じく2050年を見据えています。
なかでも、2050年には、現在、人が居住している地域の約2割が無居住化することで国土管理の悪化や大規模自然災害、自然環境・景観悪化が想定されており、そうした課題への対応が計画に反映されているのが特徴です。
また、重要ワードとして、30by30目標が掲げられています。30by30とは、2030年までに生物多様性の損失を止め、反転させるネイチャーポジティブの実現に向け、2030年までに陸と海の30%以上を健全な生態系として効果的に保全しようとする目標のこと。
これらに加えて、国土形成計画同様に災害抑止に向けた対応が規定されています。
今後、新しい国土利用計画(全国計画)を踏まえて、都道府県が策定する「土地利用基本計画(作成は義務)」が見直され、さらに当該計画を踏まえて、関連する個別法に基づいた計画との調整・調和・連携が図れる予定です。

なお、都市計画の場合には、都道府県・政令指定都市策定の「都市計画区域マスタープラン」・市町村策定の「都市計画マスタープラン」の策定時に国土利用計画(国土形成計画の概念を含めて)を踏まえた見直しが実施されます。
関連記事
文字量が5000文字を超えてしまったのでまた次回以降で書きたいと思います。
両計画について閣議決定行った際の資料URLはこちら
>>>https://www.mlit.go.jp/report/press/kokudoseisaku03_hh_000239.html


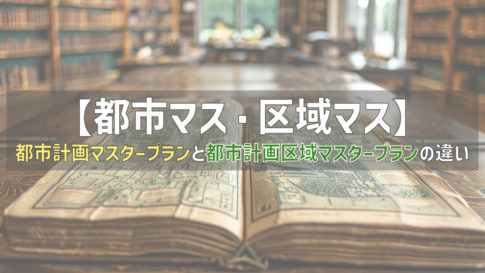





・新時代に地域力をつなぐ国土
・シームレスな拠点連結型国土