この記事では、特定行政庁の権限として行うことができる大規模災害後の建築制限に関して分かりやすく解説を行っています。建築士試験などに出題される法令ですので、そのことを踏まえて解説を行っています。
こんにちは!YamakenBlogへようこそ!
YamakenBlogでは、建築基準法や都市計画法、宅建業法など、まちづくりに関連する難解な法律を、元行政職員の私が分かりやすく解説しています。
このブログは、建築・不動産業界のプロから、家づくりを計画中の方、店舗立地を検討している方まで、誰でも役立つ情報が満載です!
ぜひ、ブックマーク登録を行い、今後も役立つ情報を受け取ろう!
*このサイトリンクはブログやメール、社内掲示板などで自由に使っていただいて大丈夫です!お気軽にどうぞ!
大規模災害後の建築制限

法律は、建築基準法第84条(被災市街地における建築制限)に規定されているルールです。
(被災市街地における建築制限)
建築基準法第84条
第84条 特定行政庁は、市街地に災害のあつた場合において都市計画又は土地区画整理法による土地区画整理事業のため必要があると認めるときは、区域を指定し、災害が発生した日から1月以内の期間を限り、その区域内における建築物の建築を制限し、又は禁止することができる。
2 特定行政庁は、更に1月を超えない範囲内において前項の期間を延長することができる。
目的としては、大規模火災、大規模地震や津波、洪水により大きな災害後(市街地)に置いて、行政側で復興計画(都市計画事業)を立てて事業化するまでの期間、建築制限を行うためです。
仮にですが、復興計画に進む前に、住民や民間事業者が無秩序に再建してしまった場合に、次にくる災害に備えるための適切な市街地の形成を阻害するためです。このルールにより、災害が発生した日から1ヶ月以内の期間、建築制限・禁止することができるとされます。また、この1ヶ月を超えない範囲においてさらに最大で1ヶ月を延長することが可能とされます。
つまり、災害後2ヶ月間、建築を制限・禁止することが可能です。
指定することができるのは特定行政庁となります。
この法律の対象としている区域は都市計画区域内です。
補足:大規模災害があれば2ヶ月はあっという間
実際、実務上は2ヶ月以内に復興計画に関して都市計画決定するのは時間的に不可能です。
都市計画決定には住民への説明会や公聴会、縦覧、都市計画審議会等の手続きが必要となるため、最短でも3〜4ヶ月は必要と考えられます。特に大規模災害後では、復興の前に救助を行うため、
このため、実務上は被災した市街地の地権者に対して、復興計画に基づく都市計画事業を実施するため、すぐに再建しないよう任意でお願いするしか方法がないのが実情です。このほか、災害危険区域を指定する方法もありますが、これに関しても2ヶ月というのは非常に短い期間です。
「2ヶ月以内に住民合意だなんて無理ですね」というのが実務経験者の本音です。
2011年の東日本大震災では、特別措置法が制定されたことにより、期間を特別に延長することが可能となりました。この特措法では、先ほど説明した建築基準法第84条の規定に関わらず、建築制限・禁止することができることが可能になった(最大で11ヶ月)
参考法令↓↓↓
(被災市街地における建築制限)
東日本大震災により甚大な被害を受けた市街地における建築制限の特例に関する法律(抜粋)
第一条 特定行政庁は、平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震により市街地が甚大な被害を受けた場合において、都市計画又は土地区画整理法による土地区画整理事業のため必要があり、かつ、当該市街地の健全な復興を図るためやむを得ないと認めるときは、建築基準法第84条の規定にかかわらず、被災市街地復興特別措置法第5条第1項各号に掲げる要件に該当する市街地の土地の区域を指定し、期間を限り、その区域内における建築物(建築基準法第2条第1号に規定する建築物をいう。第4項及び次条第1項において同じ。)の建築(建築基準法第2条第13号に規定する建築をいう。第4項において同じ。)を制限し、又は禁止することができる。
2 前項の規定による制限又は禁止は、平成23年9月11日までの間に限り行うことができる。
3 特定行政庁は、特に必要があると認めるときは、更に2月を超えない範囲内において第1項の期間を延長することができる。この場合において、延長後の期間の満了の日が平成23年9月11日後となるときにおける前項の規定の適用については、同項中「平成23年9月11日」とあるのは、「次項の規定による延長後の期間の満了の日」とする。
まとめ
まとめますと、建築基準法第84条の規定により、特定行政庁は、市街地(都市計画区域内)で発生した大規模災害後に都市計画や土地区画整理事業を行うために必要な場合には最大で2ヶ月間、建築制限・禁止する区域を定めることが可能となります。
とはいえ、実際には、2011年3月に発生した東日本大震災のようにまずは救助が優先されるため、その救助期間は2ヶ月を超えてしまうため、特措法をつくって、建築を制限・禁止する期間を延長させることになります。
ということで以上となります。
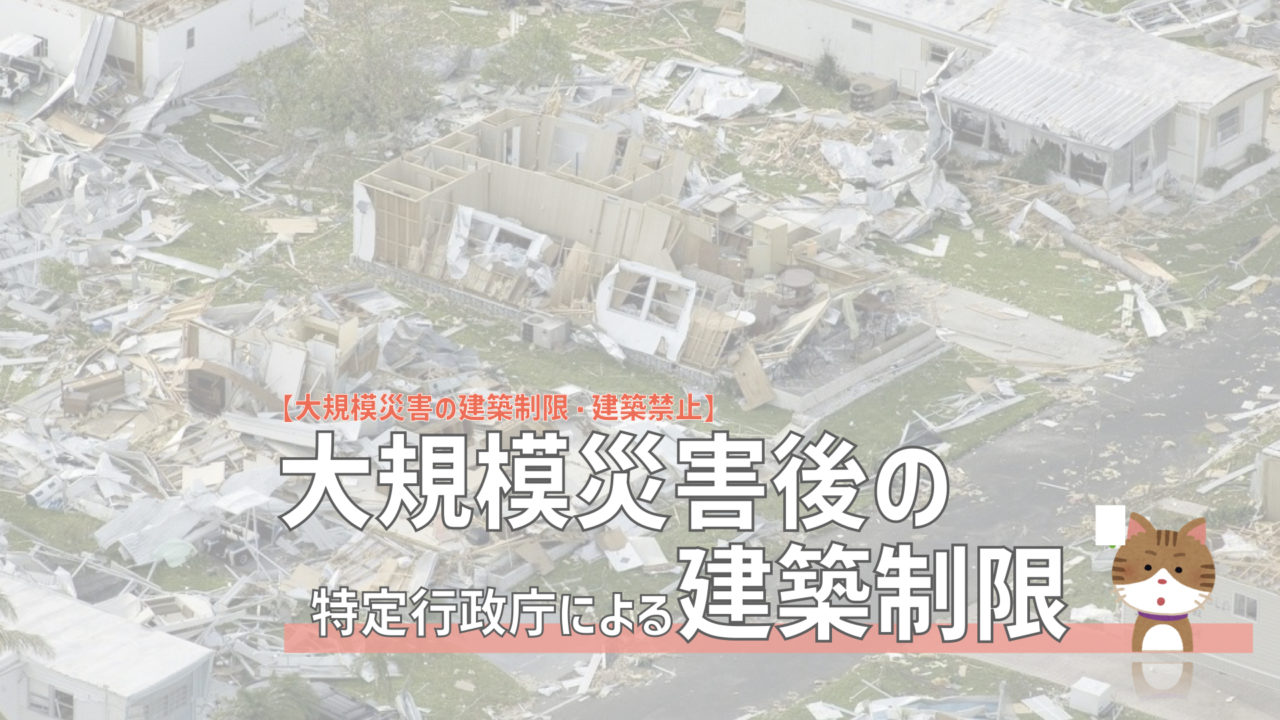
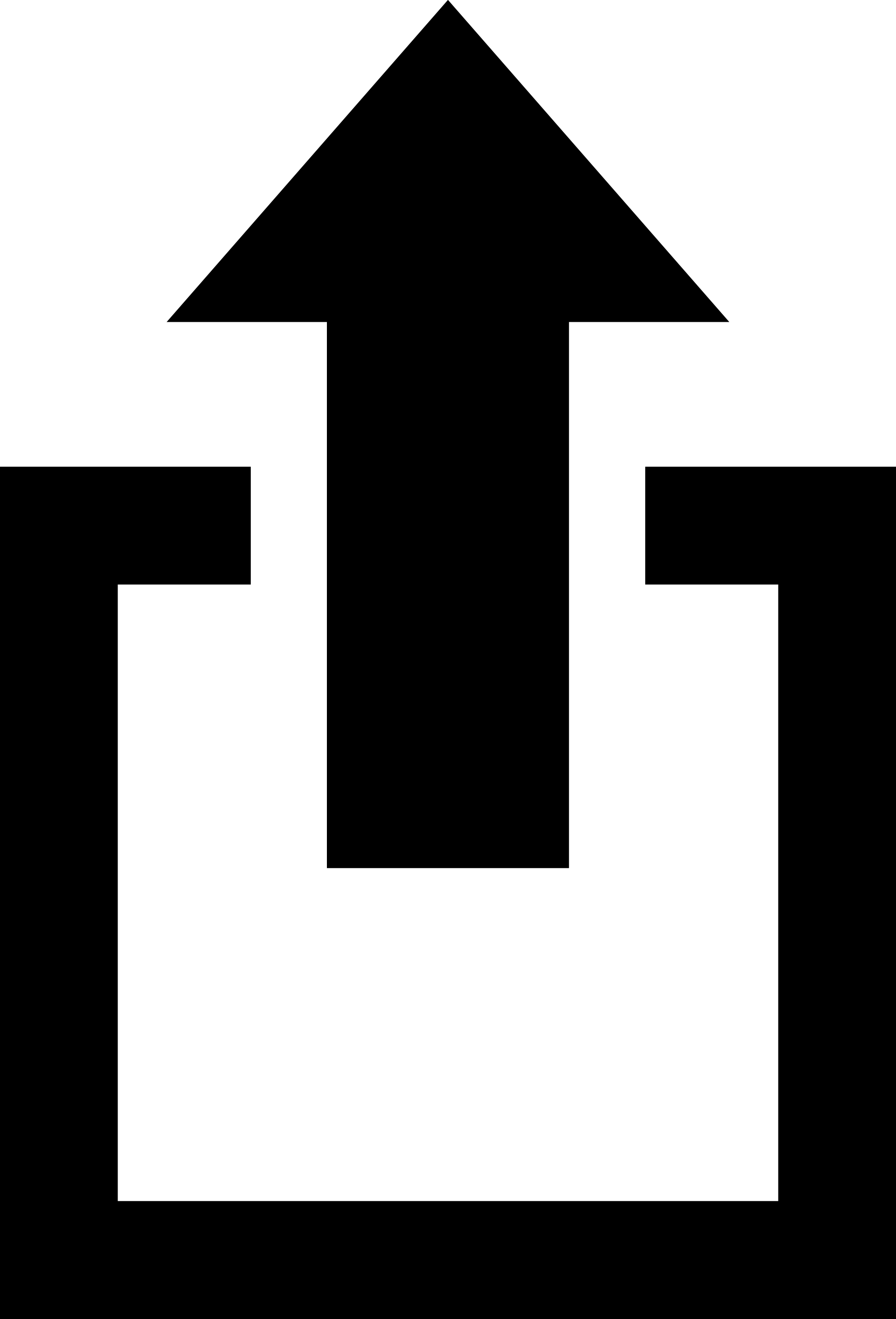 共有アイコンをタップし、「ホーム画面に追加」を選択してください。
共有アイコンをタップし、「ホーム画面に追加」を選択してください。



