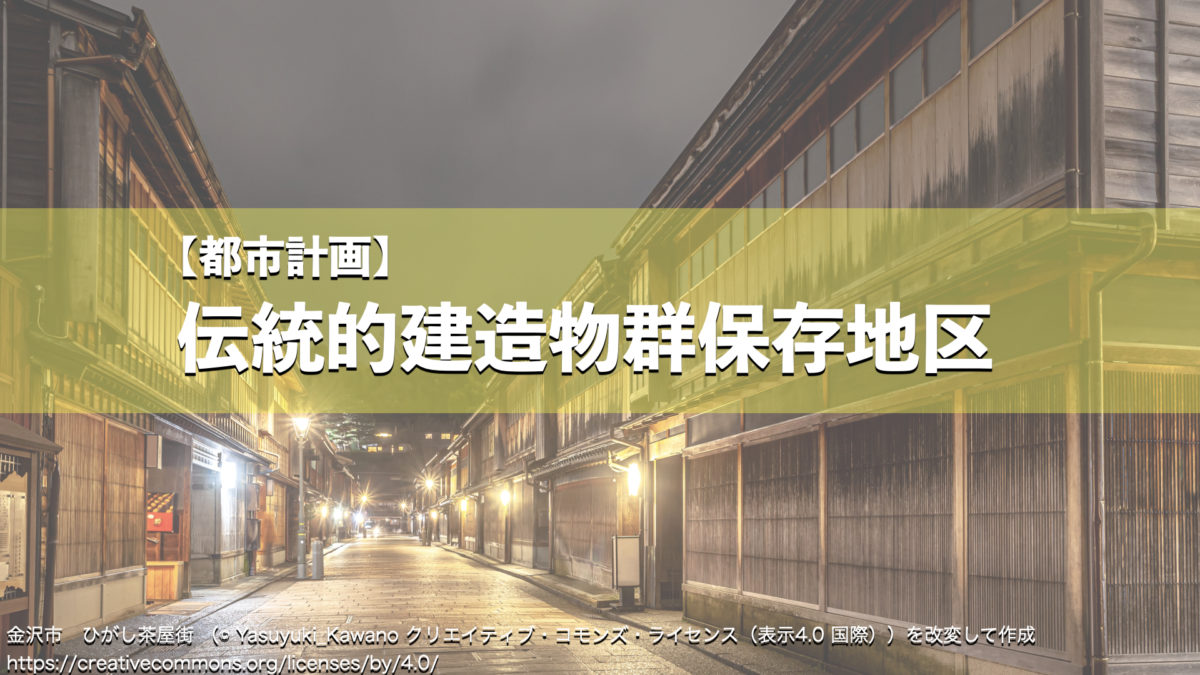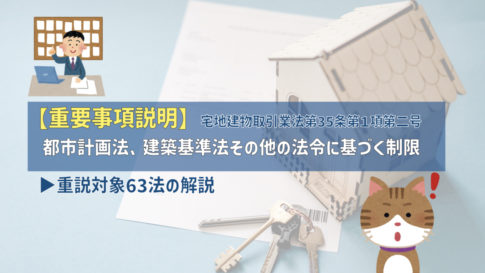この記事では、地域地区に区分される都市計画「伝統的建造物群保存地区」について分かりやすく解説しています。よく試験等で出題される建築基準法との関係性についても解説を行っています。
こんにちは。やまけん(@yama_architect)です^ ^
YamakenBlogでは、建築や都市計画、不動産取引に関して業務に役立つ豆知識を発信しています♪
建築基準法や都市計画法といった都市づくりに欠かせない法律は、複雑かつ難解なので理解に苦しみますよね。そのような方のために、法律を上手に活用してビジネスや生活に活用してもらいたいと思いつくったブログです。
良かったらブックマーク登録して毎日、遊びに来てくれるとブログ運営の励みになります♪
伝統的建造物群保存地区とは?
創設は昭和50年となります。
文化財保護法の改正により歴史的な建造物や街並みを保存するための「伝統的建造物群保存地区」の制度が設けられた比較的新しい都市計画となります。
都市計画法と文化財保護法が関係する都市計画となります。
都市計画が主体で行われるツールというよりは、文化財保護法に基づく歴史的な街並みの保存のために用いられるものと考えて頂くのが良いと思います。
都市計画法第8条第1項第十五号と文化財保護法第142条に規定されており、都市計画運用指針では、「伝統的建造物群の主として外観上認められるその位置、 形態、意匠等の特性をその周囲の環境と併せて保存すること」を目的とすると書かれており、伝統的建造物群及びこれと一体をなしてその価値を形成している環境を保存するため定める地域地区とされています。
つまり、歴史的に貴重な建造物の集合体(群)と街並みの環境を保存しようとするものです。文化財保護法では次のように指定の考え方が示されています。
市町村は、都市計画法第5条又は第5条の二の規定により指定された都市計画区域又は準都市計画区域内においては、都市計画に伝統的建造物群保存地区を定めることができる。この場合においては、市町村は、条例で、当該地区の保存のため、政令の定める基準に従い必要な現状変更の規制について定めるほか、その保存のため必要な措置を定めるものとする。
文化財保護法第143条第1項(伝統的建造物群保存地区の決定及びその保護)
基本的な考え方として、都市計画区域又は準都市計画区域内に定めることができ、具体的な規制の内容については、市町村の条例で定めることとされています。都市計画区域(準都市計画区域を含む)内であればどこでも定めることが可能でs。
*都市計画区域外についても条例を定めることで当該保存地区を定めることも可能(文化財保護法第143条第2項。注:都市計画ではない)
このため、市町村が定める条例では、伝統的建造物群保存地区内での建築物・工作物の建築等や修繕、模様替え又は色彩の変更でその外観の変更、さらに、宅地の造成その他の土地の形質の変更、木竹の伐採、土石の類の採取などに関して制限が定められています。
例えば、不動産取引や建築設計の事前調査において、都市計画で伝統的建造物群保存地区が指定されていることがわかれば、具体的な制限は市町村条例を確認しないとなりません。
国が毎年公表している都市計画現況調査によると令和3年3月末時点で67都市、84地区、1,361.1haが指定されています。なお、指定数としては近畿地方が最も多く18地区指定されています。
また、伝統的建造物群保存地区に加えて文部科学大臣が選定することができる「重要伝統的建造物群保存地区」については、文部科学省によると令和3年8月時点で126地区が指定されているそうです。
ここでいう126地区と都市計画で指定される84地区の差は、単純に都市計画区域内(準都市計画区域を含む)が84地区、残りの地区が都市計画区域外ということです。
歴史的な建造物群が残っている地域には比較的都市化が進んでいない都市計画区域外が多いということです。
重要伝統的建造物群保存地区とは?

重要伝統的建造物群保存地区の選定には、”重要”の記載が無い「伝統的建造物群保存地区」の都市計画決定が必要となります。指定した上で国から選定を受けるという運び。
選定基準としては、次のいずれかに該当すればよく。市町村では事前に保存対策調査を行う必要があります。*保存対策調査:歴史や現況の調査を行い文化財としての価値及び住民意向の把握など
- 伝統的建造物群が全体として意匠的に優秀なもの
- 伝統的建造物群及び地割がよく旧態を保持しているもの
- 伝統的建造物群及びその周囲の環境が地域的特色を顕著に示しているもの
伝統的建造物群保存地区のメリットは、歴史的な建造物群の保存にあります。
特に文化財保護法第146条において「国は、重要伝統的建造物群保存地区の保存のための当該地区内における建造物及び伝統的建造物群と一体をなす環境を保存するため特に必要と認められる物件の管理、修理、修景又は復旧について市町村が行う措置について、その経費の一部を補助することができる。」と規定されており、市町村は国から支援を受けることが可能となっています。
市町村は,伝統的建造物群保存地区を決定し,地区内の保存事業を計画的に進めるため,保存条例に基づき保存活用計画を定めます。国は市町村からの申出を受けて,我が国にとって価値が高いと判断したものを重要伝統的建造物群保存地区に選定します。
▶︎▶︎▶︎重要伝統的建造物群保存地区一覧(文化庁外部リンク)
こちらの書籍は2010年と若干古いですが、86地区がまとめられているので伝統的建造物群保存地区を深く知りたい方にはおすすめです。
伝統的建造物群保存地区と建築基準法との関連
伝統的建造物群保存地区内では、歴史的な建造物を保存するため建築基準法の一部を適用しないことが可能となっています。緩和にあたっては、市町村による建築条例化+国土交通大臣承認が必要となります。
なお、緩和される内容としては、防火や採光、接道、建蔽率・容積率などになります。
(伝統的建造物群保存地区内の制限の緩和)
建築基準法第85条の3
第85条の3 文化財保護法第143条第1項又は第2項の伝統的建造物群保存地区内においては、市町村は、同条第1項後段(同条第2項後段において準用する場合を含む。)の条例において定められた現状変更の規制及び保存のための措置を確保するため必要と認める場合においては、国土交通大臣の承認を得て、条例で、第21条から第25条まで、第28条、第43条、第44条、第52条、第53条、第55条、第56条、第61条、第62条及び第67条第1項の規定の全部若しくは一部を適用せず、又はこれらの規定による制限を緩和することができる。
- 21条:大規模木造の主要構造部
- 22条・24条:屋根不燃区域
- 23条:外壁の準防火性能(延焼の恐れのある部分)
- 25条:大規模木造の外壁・軒裏の防火構造(延焼の恐れのある部分)
- 28条:居室の採光及び換気
- 43条:建築物の接道
- 44条:道路内建築制限
- 52条:容積率
- 53条:建蔽率
- 56条:斜線制限
- 61条:防火地域及び準防火地域の構造
- 62条:防火地域及び準防火地域の屋根
- 67条第1項:特定防災街区整備地区内の耐火建築物等
その他の役立つ情報❶:重要事項説明の対象
伝統的建造物群保存地区の指定及び条例に関しては、不動産取引における重要事項説明の対象となっていますので、事前に都市計画・条例の有無を確認し、都市計画の範囲やその内容、条例で定められている規制・制限に関して説明する義務があります。
▶︎▶︎▶︎参考記事