この記事では、建築基準法における工事着手の考え方について説明を行っています。
建築基準法第6条第1項では、「工事着手する前に建築確認を受ける」ことが求められているので、どのような行為が工事着手に該当するのか監理者・設計者としては気になるところですよね。
そこで、国の通知をもとに何をもって工事着手とするのか調べてみました。
こんにちは。やまけんです^ ^
YamakenBlogでは、建築や都市計画、不動産取引に関して業務に役立つ豆知識を発信しています♪当ブログの運営を行っている私は元特定行政庁の職員として多くの建築物の指導を行っていましたのできっとこの経験があなたのお役に立てるはずです。
また、当ブログは建築基準法や都市計画法といった都市づくりに欠かせない法律は、複雑かつ難解なので理解に苦しみますよね。そのような方のために、法律を上手に活用してビジネスや生活に活用してもらいたいと思いつくったブログです。
良かったらブックマーク登録して毎日、遊びに来てくれるとブログ運営の励みになります♪
工事着手のポイント
工事着手の解釈としては、建築物の基礎工事(根切りや本杭)に係る工事のことをいいます。
一般的な考え方は、次の書籍(https://www2.icba.or.jp/products/detail.php?product_id=495)においてまとめられていますが、特定行政庁と言って、各自治体が最終的に判断を行っています。
建築法規に関する判断は、民間の建築審査機関では最終的判断を行うことが出来ませんので、”着工に関する行為の判断を相談する場合には”必ず着工する所在地の自治体の判断を仰ぐ必要があります。
私も過去に特定行政庁で働いていた経験がありますので、着工の判断を求められることがありました。というのも、現場担当と建築確認申請の担当者との間で調整が上手くいかずに、勝手に現場が進んでしまうことで違反建築物となってしまう事がある為です。
現場は、施主さんへの引き渡し日の関係上、工程どおり進めたいのに申請担当の方で審査機関から指摘等を受けて調整が上手くいかない、または、申請担当者は現場側に建築確認済証が交付されるまで建築着工を待てと言っているのに現場が待たないとか…。
その他にも様々な相談を受けてきましたが、結局は調整が上手く進んでいないために起きる事態です。違反となってしまうと適法(法律に適合)に持っていくのは非常に難しいです。一般的な特定行政庁の判断では、建築基準法第12条第5項の対応となります。
本題に戻します。
そもそも何故、そこまで「着工」の判断が問題になるのかという点ですが、建築基準法第6条第1項では、次のように書かれているからです。この内容が例えば建築確認済証の交付を持って着工となっていると違うんですけど…
法律では、「建築しようとする場合、確認申請を提出して建築主事の確認を受け、確認済証の交付を受けなければならない」とされています。
(建築物の建築等に関する申請及び確認)
建築基準法第6条第1項(抜粋)
建築主は、第一号から第三号までに掲げる建築物を建築しようとする場合(増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第一号から第三号までに掲げる規模のものとなる場合を含む。)、〜(略)〜その計画が建築基準関係規定(この法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定(以下「建築基準法令の規定」という。)その他建築物の敷地、構造又は建築設備に関する法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定で政令で定めるものをいう。以下同じ。)に適合するものであることについて、確認の申請書を提出して建築主事の確認を受け、確認済証の交付を受けなければならない。当該確認〜(略)〜同様とする。
以上から、着工の判断が非常に重要な判断になるということ。
着工の判断:国の技術的助言
着工の判断については、昭和41年に次のような文書が建設省住宅局から発出されています。
とても参考になる通知文で、「昭和41年3月17日住指発第83号」といいます。
この通知文書では、地耐力試験実施のために土地を掘削するのみでは、建築工事の着手には該当しないとするものであり、いわゆる建築物の設計のための地盤調査は工事の着手には該当しないとしたものです。
○照会内容
建築物を建築しようとする場合において予定敷地の地耐力を予想して設計し、当該敷地の地盤を掘削して地耐力試験を実施することは、建築工事の着工の時点と看做(*読み:みな)されるかどうか、ご教示願います。○回答内容
昭和41年3月17日 住指発第83号
地耐力試験実施のために土地を掘削するのみでは、未だ建築物基準法にいう建築工事の着手に該当しない。
以上のことから、試験杭も同様に工事の着手には該当しないと考えて良いです。実際、私もそのように判断しておりました。
*試験杭をそのまま本杭として使用することを前提としての場合には特定行政庁への判断が必要。
補足:仮設工事は工事着工?
では、仮設工事はどうか。
特定行政庁や日本建築行政会議が示している考え方においては、「現場の整地及びやり方」、「現場の仮囲いの設置」、「現場事務所の建設」は工事の着手には該当しないとすることが一般的となっています。
また、「地鎮祭」も工事の着手に該当しないと考えるのが妥当と言えます。
ですので、建築確認申請の確認がおりる前に、上記のような仮設工事に着手していても問題はありません。ですので、建築物の建築(試験杭や地盤調査を除く基礎工事)に着手場合に建築基準法上の工事着手と考えておけばOKです。
ただし、近隣住民等からは建築確認看板が掲示されていないことに対する指摘はあるかもしれませんので、そうしたケースにあらかじめ対応しておくことがポイントかと思います。
(例えば、建築確認済番号と日付、建築主事名を抜きにして掲示しておくなど)
過去の判例にみる注意点
しかしながら、過去の判例では、根切工事は、建築物の建築の工事が行われていることが、外部から客観的に認識できるとはいえないとして、法第3条第2項でいう「工事中の建築物」に当たらないとする解釈もあります。
つまり、建築工事に着手していないということ。
『外部から客観的に認識』できるかできないのかが、工事着手に該当するかどうかの判断となりそうです。
例えば、建築物の本体部分に関する工事に着手すれば着手と判断されると考えられますが、土留ための擁壁工事などは建築物に着手しているとは言えないということだと思います。
まとめ
基本的には、日本建築行政会議で示している考え方(次のような考え方)で良いと思われます。
ですが、建築基準法でいう工事の着手は、一般・世間的にいう”着手”とは異なる場合も過去の判例で示されているので、建築主事・特定行政庁に確認するのが一番望ましいと考えられます。
特に、法令改正がある場合における、既存不適格となる場合には留意しておくべきかなと思います。
まとめると、客観的に工事着手と言えるような場合には着手として判断される可能性が高いと考えられますので、法令改正等で駆け込み着手を行うような場合には注意が必要です。
ということで以上となります。参考となれば幸いです。
補足:長期優良住宅では工事着手後は認定を受けられない
近年、認定件数が増加している長期優良住宅(新築)ですが、工事着手してしまうと認定を受けることはできませんので、申請時期を誤ったとか、工事着手後でも問題ないと思っていたみたいなことにならないようご注意ください。

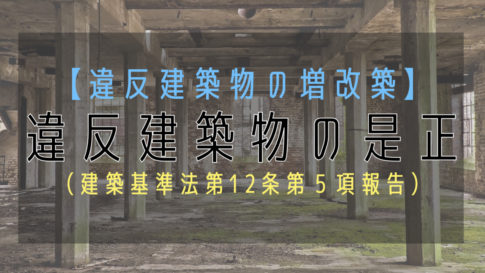





*一般的に建物本体の建築のための工事(地盤改良や基礎工事)であれば着工と判断されると考えれます。