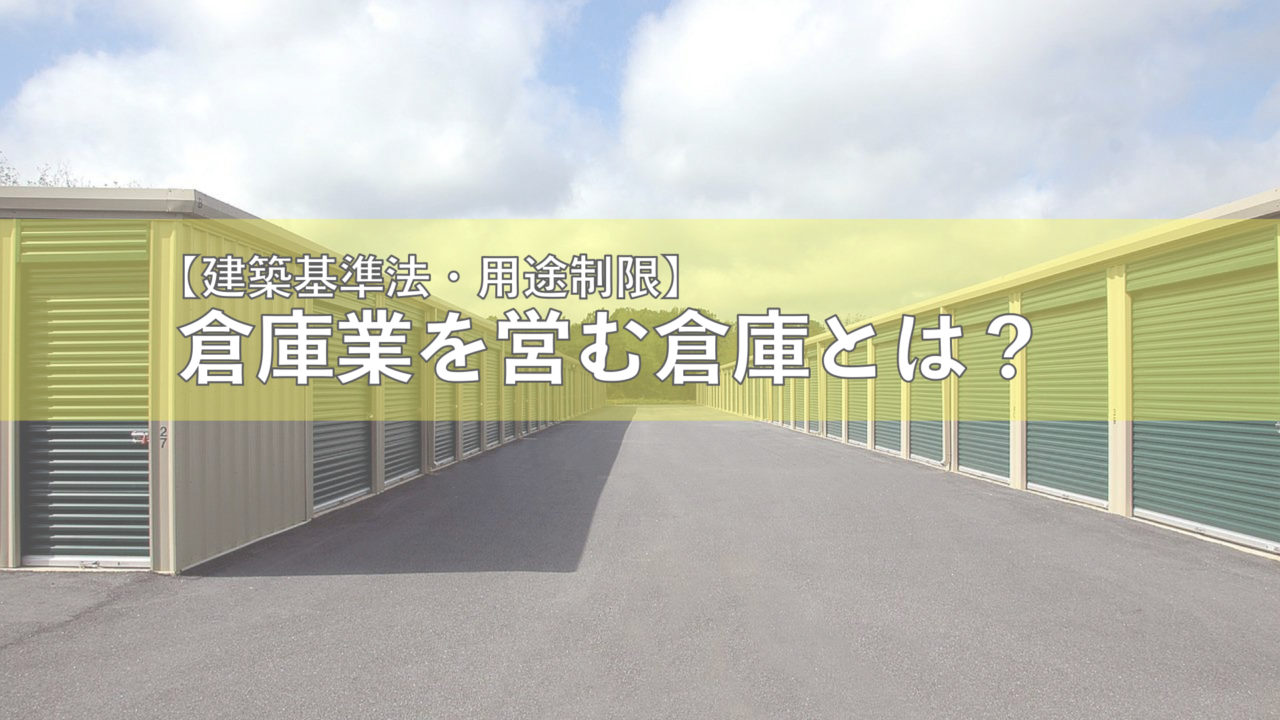この記事では、
上記の疑問に答える記事となっています。
こんにちは! YamakenBlogです。
YamakenBlogでは、建築や都市計画、不動産取引に関して業務に役立つ豆知識を発信しています♪
建築基準法や都市計画法といった都市づくりに欠かせない法律は、複雑かつ難解なので理解に苦しみますよね。そのような方のために、法律を上手に活用してビジネスや生活に活用してもらいたいと思いつくったブログです。
良かったらブックマーク登録して毎日、遊びに来てくれるとブログ運営の励みになります♪
目次
倉庫業を営む倉庫とは?

倉庫といっても一概に括れないのが、この”倉庫”です。
さらにさらに倉庫は、建築基準法では特殊建築物に該当するため、防火関係での法規制が厳しいですから立地検討に当たっては慎重な判断が求められます。
・『倉庫コンテナを利用して貸し倉庫業をやりたい』
・『自己の敷地内にトランクルームを設置したい』
など、、、様々なケースが想定できますが、基本的な土地の有効活用かと思います。
倉庫業を営む倉庫とは、まず原則として、倉庫業とあるように基本的には、倉庫業法に該当するものが建築基準法でいう倉庫業を営む倉庫にあたるという考えです。
倉庫業法では、倉庫業の定義を以下のように定めています。
端的にいうと、他人の物品を保管する営業倉庫のことです。
例えば、他人から料金をとって荷物を預かり、その荷物を自分の倉庫で保管する行為です。
倉庫業に該当する場合には、倉庫業法が適用されます。
ポイントは、”寄託を受けた”という部分です。
賃貸借であるレンタル倉庫との違いはココです。
(定義)
倉庫業法第2条
第2条 この法律で「倉庫」とは、物品の滅失若しくは損傷を防止するための工作物又は物品の滅失若しくは損傷を防止するための工作を施した土地若しくは水面であつて、物品の保管の用に供するものをいう。
2 この法律で「倉庫業」とは、寄託を受けた物品の倉庫における保管(保護預りその他の他の営業に付随して行われる保管又は携帯品の一時預りその他の比較的短期間に限り行われる保管であつて、保管する物品の種類、保管の態様、保管期間等からみて第6条第1項第四号の基準に適合する施設又は設備を有する倉庫において行うことが必要でないと認められるものとして政令で定めるものを除く。)を行う営業をいう。
3 この法律で「トランクルーム」とは、その全部又は一部を寄託を受けた個人(事業として又は事業のために寄託契約の当事者となる場合におけるものを除く。以下「消費者」という。)の物品の保管の用に供する倉庫をいう。
なお、倉庫業は、国土交通大臣登録となっているので、登録を受けたいと考えている方は、倉庫業の登録申請などの業務を行なっている行政書士さんなどに相談しましょう。
倉庫業を営む倉庫を判断する上で注意点があります。
倉庫業を営む倉庫を判断する上での補足
建築基準法における倉庫業を営む倉庫 = 倉庫業法に規定する倉庫
という明確な定義は、建築基準法には記載されていません。
そもそも倉庫業を営む倉庫の立地制限を行う理由として、不特定多数が利用することが想定され、頻繁に自動車が往来することで、自動車交通量が増加し、住環境が悪化する恐れがあるために、低層住居等では建築することができない規定になっています。
一方で、倉庫業を営まない自己用倉庫では、自動車交通量の増加は限定的であり、利用者は特定されるため、倉庫業を営む倉庫よりも住環境の悪化は、営まないよりも避けると考えられます。
とはいえ、業ではなくても利用形態によっては、業と同程度であるケースも否定できません。
そのため、倉庫業法の適用を受けない場合でも、建築基準法でいう倉庫業を営む倉庫に該当する可能性を完全には排除できないですから、最終的な用途の判断は、必ず特定行政庁に確認しましょう。
(補足)日本建築行政会議における倉庫業営む倉庫の考え方
>>他人の物品を保管、貯蔵することを業としている場合には、倉庫業を営む倉庫に該当する
要点をまとめると、他人の物品を預かることを業(料金を徴収して営む形態)としている倉庫が、倉庫業を営む倉庫に該当すると考えてよいと思われます。”業”に該当しているかどうかが判断のポイントとなります。
なお、倉庫の所有等の別(自己所有、他人物を賃借)は、建築基準法では関係ないため、倉庫業でない限りは、所有権等は関係ありません。
次に自身が所有する倉庫を賃貸する場合の取り扱いです。
自己倉庫を賃借する場合
上記の説明にあるとおりとなりますが、賃借により、倉庫業を営まなければ倉庫業を営む倉庫には該当しないです。
*ただし、自己倉庫が大規模で利用形態が業と同じように不特定多数が利用する場合などは、注意が必要となります。
そのため、自己倉庫を他者に貸す時は、用途地域が倉庫業を営む倉庫が規制される地域であれば、重要事項説明時に、倉庫業を営む倉庫では利用できないと、しっかりと(確実に)説明する必要があります。
用途地域の中では、どこの用途地域で建築することが可能なのか
倉庫業を営む倉庫が建築することができる用途地域は以下のとおり
| 建築することができる地域 | 建築することができない地域 |
|---|---|
| ・準住居地域 ・近隣商業地域 ・商業地域 ・準工業地域 ・工業地域 ・工業専用地域 | ・第一、二種低層住居専用地域 ・第一、二種中高層専用地域 ・第一、二種住居地域 ・田園住居地域 |
(注1)市町村によっては、用途地域の制限以外に、地区計画や特別用途地区等により、倉庫業を営む倉庫を規制している場合ある。
(注2)準住居、近隣商業、商業地域では、原動機を使用する工場用途にも供する場合には床面積制限あり。
(注3)保管する物品が危険物である場合は、別途規制あり(工業・工業専用地域を除く)
上記の他、最近では物流効率化法に基づき市街化調整区域(インターチェンジ近接型)での建築も可能となっています。工業系用途地域での選択が難しい場合には都市計画法の特例(市街化調整区域での開発許可)も視野に入れて検討してみることもありです。
※検討の際には、許可手続き等までに役所等と複雑な協議・調整が必要となるため都市計画法に精通したコンサルを入れることをおすすめします。
コンテナ倉庫を設置する際には建築確認申請が必要?

コンテナ倉庫の取り扱いについては、過去に国からの通知(平成16年12月6日国住指第2174号)により、建築基準法第2条第一号に規定する建築物に該当するという見解がなされています。
そのため、コンテナ倉庫であっても、建築物に該当するため、建築確認申請が必要ですし、建築物のため、当然、用途制限も適用されます。
その場合、一部の住居系用途地域では、倉庫業を営まない倉庫であっても、単独での倉庫建築が認められない地域があるので注意してください。
▶︎▶︎▶︎こちらの記事で用途地域毎の建築制限を確認することができます。
倉庫業を営む倉庫の床の積載荷重
「倉庫業を営む倉庫」については、構造計算を行う場合の床の積載荷重について、他の用途とは異なる基準が設けられています。
一般的には、建築基準法施行令第88条第1項において、『建築物の各部の積載荷重は、当該建築物の実況に応じて計算しなければならない。』と規定されており、”建築物の実況に応じて設定する”こととなりますが、3,900N/㎡未満となる場合でも3,900Nとする必要があります。
倉庫業を営む倉庫における床の積載荷重は、第1項の規定によつて実況に応じて計算した数値が1㎡につき3,900N未満の場合においても3,900Nとしなければならない。
建築基準法施行令第88条第3項
まとめ
倉庫業を営む倉庫と倉庫の違い、また、倉庫業を営む倉庫はどの用途地域で建築することが可能なのかを解説しました。
ポイントは、”倉庫業を営む(営業倉庫)”に該当するかどうかです。また、倉庫業に該当する場合には、準住居地域以上の制限が緩い用途地域のみでしか建築することはできません。
それでは最後まで読んでいただきありがとうございました。業務の参考になれば幸いです!!
▶︎▶︎▶︎こちらの記事では大型の物流センターや物流拠点施設の用途制限について解説を行っています。