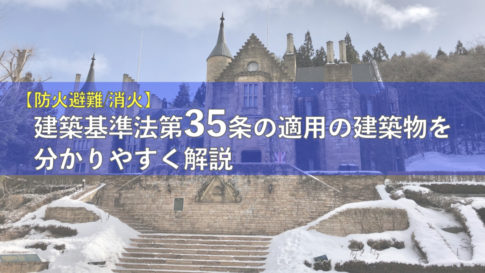この記事では、建築基準法の用語として度々登場する”無窓居室”。
その名のとおり「窓が無い部屋」のことをいうのですが、完全に窓が無いわけではなく”有効な窓”がない居室のことをいいます。
この無窓居室ですが、代表的な採光無窓や排煙無窓を含めて合計で6種類あります。この6種類を理解しておくことで建築設計や建築確認審査時のミスを防ぐことができるようになります。
こんにちは! YamakenBloigです。
YamakenBlogでは、建築や都市計画、不動産取引に関して業務に役立つ豆知識を発信しています♪
建築基準法や都市計画法といった都市づくりに欠かせない法律は、複雑かつ難解なので理解に苦しみますよね。そのような方のために、法律を上手に活用してビジネスや生活に活用してもらいたいと思いつくったブログです。
良かったらブックマーク登録して毎日、遊びに来てくれるとブログ運営の励みになります♪
今回は、「無窓居室」に関しての説明です。
目次
無窓居室の種類について
これまでにも排煙無窓については解説してきたところですが、今回は、そもそもの無窓居室の種類について解説していきます。
全部知らなくても、建築設計でもなんとかなるとは思います。
ですが、なんとなくでも知っていると、「これなんの無窓?を言ってんねん」って設計者同士の会話でより分かるようになるのと、やっぱり建築士としては避けたい建築物の設計における手戻りを少なくすることができます。
また、建築確認審査のスピードを上げることできるメリットもあります。
なお、通常の設計においては、これから説明する採光と排煙無窓、それから主要構造部の耐火構造等に関する無窓について知っていればいいのかなかなと思います。
ここから一づつ説明しします。
換気上の無窓居室
これは、建築基準法第28条第2項に規定されているものです。
規定内容としては、居室の床面積の20分の1以上の開口部を設けなければならないとするものです。この換気上の無窓居室を解除するためには、建築基準法施行令第20条の2に規定する換気設備を設けないといけないとする規定です。
(法第28条第2項)
建築基準法第28条第2項
居室には換気のための窓その他の開口部を設け、その換気に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して、20分の1以上としなければならない。ただし、政令で定める技術的基準に従つて換気設備を設けた場合においては、この限りでない。
採光上の無窓居室
これは、建築基準法第35条,建築基準法施行令第116条の2第1項第一号に規定されているものです。
ここで注意が必要なのは、住宅等の居室の採光規定である建築基準法第28条とは異なるものです。
なお、この住宅等の居室の採光規定である法第28条については、採光上必要な規定は7分の1から10分の1の範囲内で定められています。
規定内容としては、採光上、居室の床面積の20分の1以上の窓等を設けなければならないとするものです。この採光無窓となると、建築基準法第35条が適用(防火避難規定)されることとなるため、絶対に外せない法規チェックとなります。
(令第116条第1項第一号)
建築基準法施行令第116条第1項第一号
法第35条(法第87条第3項において準用する場合を含む。第127条において同じ。)の規定により政令で定める窓その他の開口部を有しない居室は、次の各号に該当する窓その他の開口部を有しない居室とする。
一 面積(第20条の規定より計算した採光に有効な部分の面積に限る。)の合計が、当該居室の床面積の20分の1以上のもの
▶︎▶︎▶︎関連する詳細記事
排煙上の無窓居室
これは、建築基準法第35条,建築基準法施行令第116条の2第1項第二号に規定されているものです。
規定内容としては、居室の床面積の50分の1以上の有効な開口部を設けなければならないとするものです。採光無窓同様にこの採光無窓となると、建築基準法第35条が適用(防火避難規定)されることとなるため、絶対に外せない法規チェックとなります。
(令第116条第1項第二号)
建築基準法施行令第116条第1項第二号
法第35条(法第87条第3項において準用する場合を含む。第127条において同じ。)の規定により政令で定める窓その他の開口部を有しない居室は、次の各号に該当する窓その他の開口部を有しない居室とする。
二 開放できる部分(天井又は天井から下方80㎝以内の距離にある部分に限る。)の面積の合計が、当該居室の床面積の50分の1以上のもの
▶︎▶︎▶︎関連する詳細記事
内装制限上の無窓居室
これは、建築基準法第35条の2,建築基準法施行令第128条の3の2に規定されているものです。
規定内容としては、床面積が50㎡を超える居室において、居室の床面積の50分の1以上の有効な開口部を設けなけばならいとするものです。
つまり、50分の1未満の場合には、内装無窓となり、内装制限が適用されます。(同令二号もありますので注意を・・・)
(制限を受ける窓その他の開口部を有しない居室)
建築基準法施行令第128条の3の2
第128条の3の2 法第35条の2(法第87条第3項において準用する場合を含む。次条において同じ。)の規定により政令で定める窓その他の開口部を有しない居室は、次の各号のいずれかに該当するもの(天井の高さが6mを超えるものを除く。)とする。
一 床面積が50㎡を超える居室で窓その他の開口部の開放できる部分(天井又は天井から下方80㎝以内の距離にある部分に限る。)の面積の合計が、当該居室の床面積の50分の1未満のもの
二 法第28条第1項ただし書に規定する温湿度調整を必要とする作業を行う作業室その他用途上やむを得ない居室で同項本文の規定に適合しないもの
主要構造部を耐火構造等にする無窓の居室
これは、建築基準法第35条の3,建築基準法施行令第111条に規定されているものです。
規定内容としては、一号と二号があります。
この無窓解除を出来ない場合には、「居室を区画する主要構造部を耐火構造とし、または不燃材料」とする必要があります。つまり、木造構造とすることが現実的に厳しくなるので注意が必要です。
施行令で定められる窓その他の開口部を融資ない居室について、一号は、採光上、居室の床面積の20分の1以上の窓等を設けなければならないとするものです。(採光上の無窓居室に同じ)。
二号は、直接外気に接する避難上有効な構造で、直径1m以上の円が内接することできる窓等、or幅75㎝以上・高さ1.2m以上の窓等を設けなければならないとするものです。
なお、近年の改正によりカッコ書きの部分が追加され、一定要件に該当するものは緩和され、無窓解除がしやすくなっています。
(令第111条第1項)
建築基準法施行令第111条第1項
法第35条の3(法第87条第3項において準用する場合を含む。)の規定により政令で定める窓その他の開口部を有しない居室は、次の各号のいずれかに該当する窓その他の開口部を有しない居室(避難階又は避難階の直上階若しくは直下階の居室その他の居室であつて、当該居室の床面積、当該居室の各部分から屋外への出口の一に至る歩行距離並びに警報設備の設置の状況及び構造に関し避難上支障がないものとして国土交通大臣が定める基準に適合するものを除く。)とする。
一 面積(第20条の規定により計算した採光に有効な部分の面積に限る。)の合計が、当該居室の床面積の20分の1以上のもの
二 直接外気に接する避難上有効な構造のもので、かつ、その大きさが直径1m以上の円が内接することができるもの又はその幅及び高さが、それぞれ、75㎝以上及び1.2m以上のもの
▶︎▶︎▶︎関連する詳細記事
敷地と道路との関係における無窓の居室
これは、建築基準法施行令第144条の5,建築基準法施行令第116条の2に規定されているものです。
この建築基準法施行令第144条の5は、敷地と道路との関係における自治体の制限の強化です。
条例によって、「敷地が接しなければならない道路の幅員や接道長など」に関して付加することができるとされています。その中に「政令で定める窓その他その他の開口部を有しない居室を有する建築物」という規定があります。ちょっとややこしいのですが、簡単にいうと、自治体の条例による無窓居室に関する制限です。
つまり、採光・排煙無窓の考え方に同じです。
自治体が制限を付加する条例をつくる際に、無窓居室についても規定することができるとしたもので、実務上は各自治体の建築基準法条例をチェックする必要があります。
(令第144条の5)
建築基準法施行令第144条の5
法第43条第3項第三号の規定により政令で定める窓その他の開口部を有しない居室は、第116条の2に規定するものとする。
[建築基準法第43条第3項第三号]
3 地方公共団体は、次の各号のいずれかに該当する建築物について、その用途、規模又は位置の特殊性により、第一項の規定によつては避難又は通行の安全の目的を十分に達成することが困難であると認めるときは、条例で、その敷地が接しなければならない道路の幅員、その敷地が道路に接する部分の長さその他その敷地又は建築物と道路との関係に関して必要な制限を付加することができる。
一〜二 (略)
三 政令で定める窓その他の開口部を有しない居室を有する建築物
無窓居室を有する建築物を計画する場合について
無窓居室がある建築物については、防火避難上の規定において、制限される内容が大幅に増えます。また、自治体によっては、条例により制限の付加を行なっている場合が多いです。
ですので、無窓居室を有する場合には、入念な法チェックが必要です。
特に木造構造の場合には、構造自体を見直しする必要性が生じる場合もあり、一から設計をやり直す結果となることもありますから留意しておき、無窓にならないよう法チェックは細心の注意を払うべきです。
無窓検討においては、防火避難規定の解説書(最新版)+建築確認申請MEMO等は必須ですので、持っていない方はこの機会での購入を推奨です。
まとめ
ということで無窓居室は全部で6種類ありますよ〜という話をしてきました。
基本的に全部大事ですが、特に排煙無窓チェックは慎重に行う必要があります。
というのも無窓解除できなかった場合には、排煙設備要求が生じるため通常の1/50解除とは異なる規定が適用されるため、垂れ壁の長さや排煙区画など、結構な手間がかかります。
それでは以上となります。参考となりましたら幸いです。