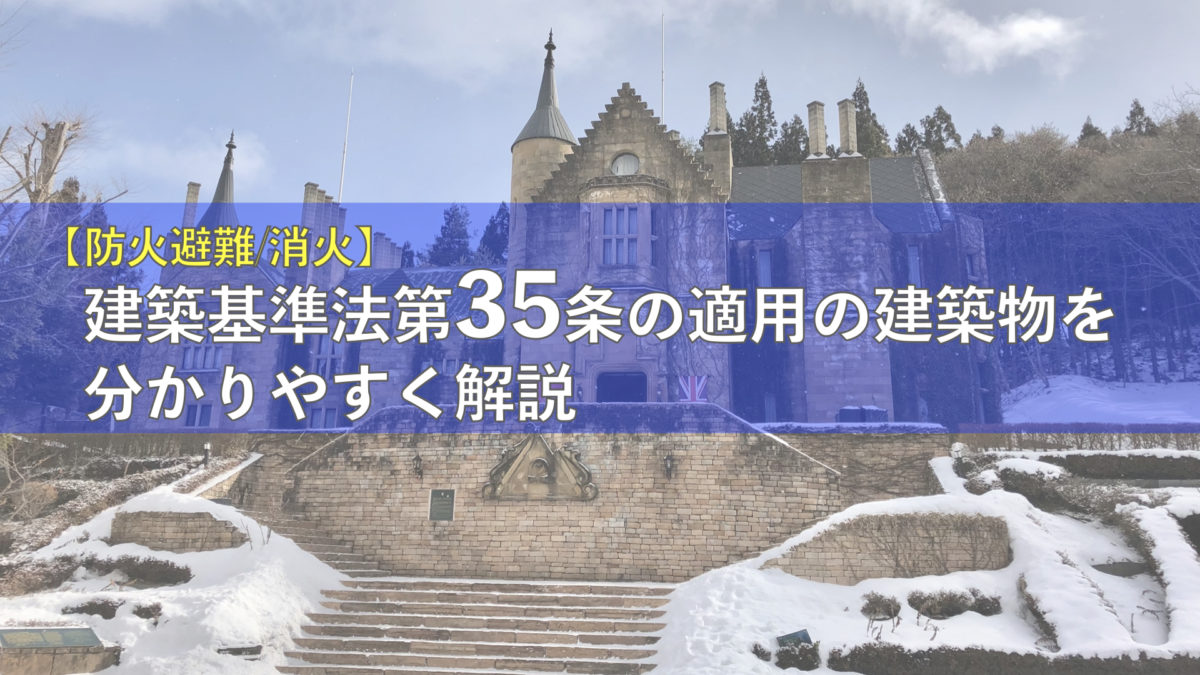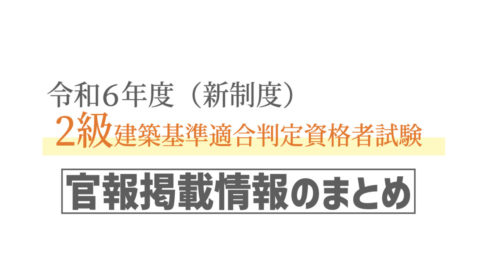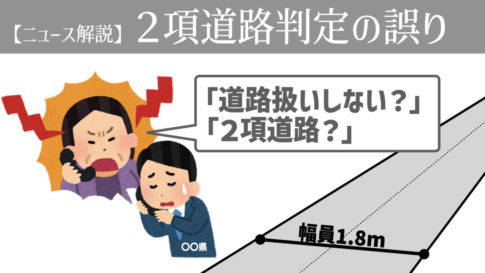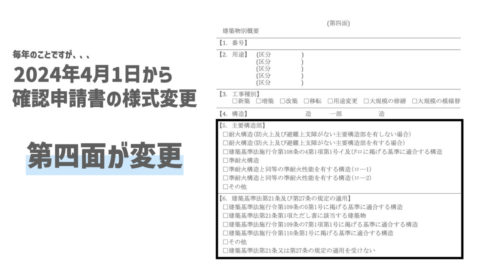この記事では、建築基準法第35条(特殊建築物等の避難と消化に関する技術的基準)の解説を行っています。
- そもそも建築基準法第35条の適用を受ける建築物とは何か。
- 建築基準法第35条の適用を受けた場合の建築物・敷地は何か。
上記の悩みを解決し、理解を深める記事となっています。
この建築基準法第35条の規定が適用されると、いわゆる防火避難規定が適用されます。
防火避難規定とは、建築物の防火対策や火災時における避難等のことをいい、その他の建築物と比べ、より人命と財産を保護することに重きが置かれています。
どのような建築物が対象になるかというと、法律では次のように記載されています。
こんにちは! YamakenBlogです。
YamakenBlogでは、建築や都市計画、不動産取引に関して業務に役立つ豆知識を発信しています♪
建築基準法や都市計画法といった都市づくりに欠かせない法律は、複雑かつ難解なので理解に苦しみますよね。そのような方のために、法律を上手に活用してビジネスや生活に活用してもらいたいと思いつくったブログです。
良かったらブックマーク登録して毎日、遊びに来てくれるとブログ運営の励みになります♪
目次
法第35条が適用される建築物
法令は、建築基準法第35条に規定されています。
[建築基準法第35条(特殊建築物等の避難及び消火に関する技術的基準)]
建築基準法第35条
別表第1(い)欄(1)項から(4)項までに掲げる用途に供する特殊建築物、階数が3以上である建築物、政令で定める窓その他の開口部を有しない居室を有する建築物又は延べ面積(同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては、その延べ面積の合計)が1,000㎡をこえる建築物については、廊下、階段、出入口その他の避難施設、消火栓、スプリンクラー、貯水槽その他の消火設備、排煙設備、非常用の照明装置及び進入口並びに敷地内の避難上及び消火上必要な通路は、政令で定める技術的基準に従つて、避難上及び消火上支障がないようにしなければならない。
法律だけ読むと分かり難いですが、大きく4つに括られており、対象となる建築物をまとめると次のとおりとなります。
①別表第1(い)欄(1)項から(4)項の特殊建築物
②3階以上の建築物
③採光・排煙無窓居室を有する建築物
④延べ面積が1,000㎡を超える建築物(敷地内全ての建築物の延べ面積合計)
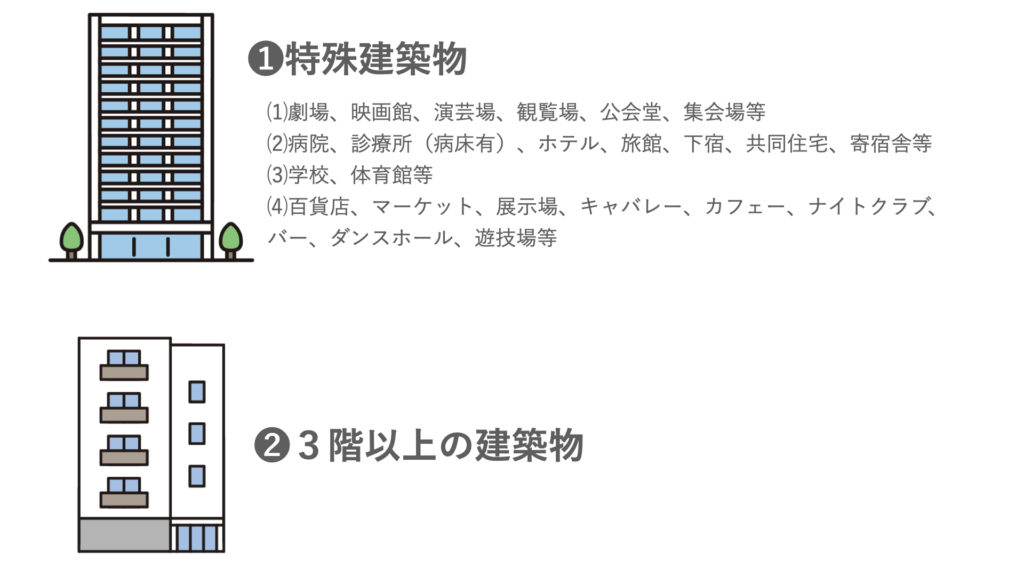
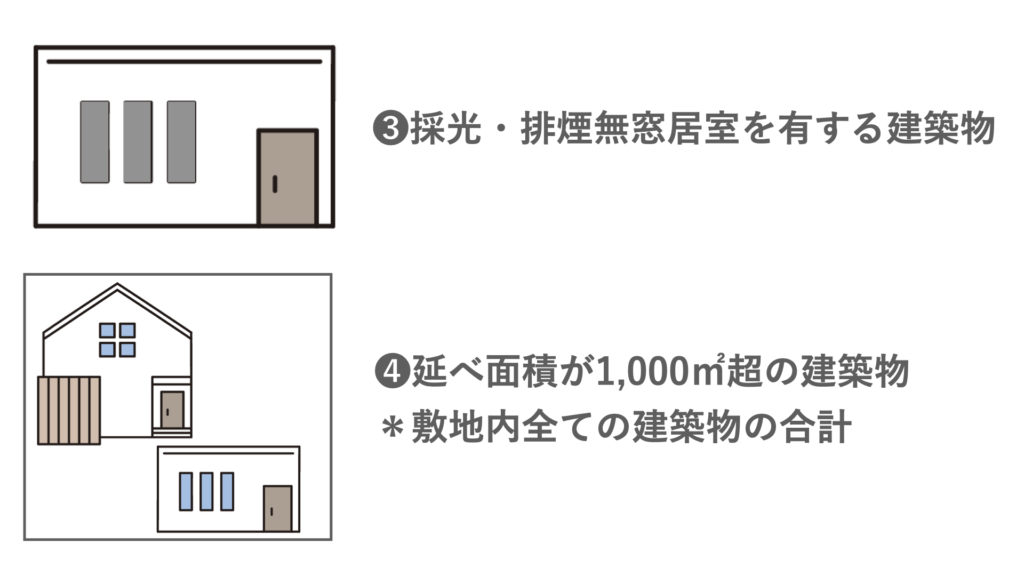
上記の①から④のいずれかに該当する建築物は、法第35条が適用される建築物となり、政令で定める技術的基準に従って、避難上及び消火上支障がないように構造や設備等を設けなければなりません。
なお、政令で定める技術的基準は、施行令の第5章(避難施設等)に規定されています。
第5章については、日本国内では一戸建ての住宅設計が多いですから普段はあまり使用しない章だと思います。建築物を審査する側は慣れていますが通常の建築設計の仕事では、建築基準法第35条を気にする機会って意外と少ないんですよね。
ただし、建築基準法第35条が適用されると、防火避難規定のチェックを行い、当然ですけど適合させなければならないので設計時での確認が必要です。罰則(後述)もありますから注意して欲しい規定となります。
なお、第5章とは、建築基準法施行令第116条の2から始まり、第128条の3まで規定されています。さらに第5章の中でも、節が設けられ、第1節から第6節まで規定されています。
簡単にまとめると次のようになります。参考にしてみて下さい。
① 別表第1(い)欄(1)項から(4)項の特殊建築物
いわゆる店舗や飲食店などの不特定多数の方が利用する建築物が対象となります。
注意点としては、法別表第1に規定される全ての建築物が対象となるのではなく、(1)から(4)までに掲げる特殊建築物が対象となる点です。
特殊建築物については、こちらの記事をご覧ください。
② 3階以上の建築物
この規定のとおり、3階以上の建築物が対象となります。
地階を除くとはないですので、1階部分が地階で地上2階建てとなれば3階建てとなりますから法第35条の適用の対象となります。
③ 採光・排煙無窓居室を有する建築物(令第116条の2第1項)
無窓居室となる建築物の部分は、建築基準法施行令第116条の2第1項に規定されています。
[建築基準法施行令第116条の2第1項]
建築基準法施行令第116条の2第1項
法第35条(法第87条第3項において準用する場合を含む。第127条において同じ。)の規定により政令で定める窓その他の開口部を有しない居室は、次の各号に該当する窓その他の開口部を有しない居室とする。
一 面積(第20条の規定より計算した採光に有効な部分の面積に限る。)の合計が、当該居室の床面積の20分の1以上のもの
二 開放できる部分(天井又は天井から下方80cm以内の距離にある部分に限る。)の面積の合計が、当該居室の床面積の50分の1以上のもの
法チェックにおいては必須の項目となっていますから必ず、採光は20分の1、排煙は50分の1と理解した上で計画建築物を確認することが重要です。
④延べ面積が1,000㎡を超える建築物(敷地内全ての建築物の延べ面積合計)
この規定のとおり、延べ床面積1,000㎡以上の建築物が対象となります。
注意点としては、敷地内全体の建築物の延べ面積の合計が対象となることです。
政令で定める技術的基準
法第35条に該当すると、次の施行令が適用されます。
なお、ややこしいのですが、建築基準法第 35条に該当する建築物は、それぞれの節で適用される建築物の規模等が規定されているので注意が必要です。*第1節については無窓の基準。
例えば、第2節の適用については、建築基準法施行令第117条に規定されています。また、排煙設備や非常用照明などもそれぞれの節で対象となる建築物の居室を規定しています。
| 節 | 節ごとの概要 | 施行令 |
|---|---|---|
| 第1節 | 総則 | ・第116条の2 窓その他の開口部を有しない居室等 関連記事:排煙設備 |
| 第2節 | 廊下、避難階段及び出入口 | ・第117条 適用の範囲(*第2節のみ適用の範囲) ・第118条 客席からの出口の戸 ・第119条 廊下の幅 ・第120条 直通階段の設置 ・第121条 2以上の直通階段を設ける場合 物品販売業を営む店舗 ・第121条の2 屋外階段の構造 ・第122条 避難階段の設置 ・第123条 避難階段及び特別避難階段の構造 ・第123条の2 共同住宅の住戸の床面積の算定等 ・第124条 物品販売業を営む店舗における避難階段等の幅 ・第125条 屋外への出口 ・第125条の2 屋外への出口等の施錠装置の構造等 ・第126条 屋上広場等 |
| 第3節 | 排煙設備 | ・第126条の2 排煙設備の設置が必要な建築物 ・第126条の3 排煙設備の構造 |
| 第4節 | 非常用の照明装置 | ・第126条の4 非常用照明装置の設置が必要な建築物 ・第126条の5 非常用照明装置の構造 |
| 第5節 | 非常用の進入口 | ・第126条の6 非常用進入口の設置が必要な建築物 ・第126条の7 非常用進入口の構造 |
| 第6節 | 敷地内の避難上及び消火上必要な通路等 | ・第127条 適用の範囲(*第6節のみ適用) ・第128条 敷地内の通路 ・第128条の2 大規模な木造等の建築物の敷地内における通路 ・第128条の3 地下街 |
罰則
建築基準法第35条に違反すると3年以下の懲役または300万円以下の罰金となります。また、第2項の”故意によるもの”であるときはさらに建築主等も罰せされますのでご注意ください。
第98条 次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。
建築基準法第98条第1項第二号、第2項
二 第20条(第1項第一号から第三号までに係る部分に限る。)、第21条、第26条、第27条、第35条又は第35条の2の規定に違反した場合における当該建築物又は建築設備の設計者(設計図書に記載された認定建築材料等(略)の全部又は一部として当該認定建築材料等の全部又は一部と異なる建築材料又は建築物の部分を引き渡した場合においては当該建築材料又は建築物の部分を引き渡した者、設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合(設計図書に記載された認定建築材料等と異なる建築材料又は建築物の部分を引き渡された場合において、当該建築材料又は建築物の部分を使用して工事を施工した場合を除く。)においては当該建築物又は建築設備の工事施工者)
2 前項第二号又は第三号に規定する違反があつた場合において、その違反が建築主又は建築設備の設置者の故意によるものであるときは、当該設計者又は工事施工者を罰するほか、当該建築主又は建築設備の設置者に対して同項の刑を科する。
本記事のまとめ
今回は以上となりますが、建築基準法第35条(特殊建築物等の避難及び消火に関する技術的基準)の規定は、あくまでも対象となる建築物を定めているだけで、具体的な基準は施行令に規定されています。
また、建築基準法施行令では第1節から第6節まで規定されており、それぞれ対象となる範囲が明示されています。計画する建築物が法第35条の適用を受けたうえで、さらに第1節から第6節のうち、何が適用されるのかを確認することが建築物を設計する上での重要なポイントとなります。
ということで以上となります。参考となりましたら幸いです。