都市再生特別措置法第81条では、多極ネットワーク型コンパクトシティの形成を進める「立地適正化計画」が規定されています。そして、この計画では、居住の誘導を図る「居住誘導区域」が定められますが、この区域に災害の発生が起きやすいハザードエリアを含めるかどうかが最近の話題となっています。
この災害ハザードエリアを「居住誘導区域」に含めるかどうかは、私たちの生活に密接に関係してきますので、実際、どうするべきなのかを考察してみました。
こんにちは!やまけんといいます。
普段、YamakenBlogでは、建築や都市計画、不動産に関して業務に役立つ豆知識を発信しています。
はじめに立地適正化計画についての知識を深めたい方はこちらの記事もお読みください。
>>【立地適正化計画とは?】立地適正化計画の本質や目的を知るお手伝いを行います。
居住誘導区域とは?
居住誘導区域とは、その名のとおり居住機能を誘導していく区域のことです。
法律は、都市再生特別措置法第81条第2項第二号に規定されています。
法律上の定義としては、「都市の居住者の居住を誘導すべき区域」とされています。
もっと厳密かつ簡潔にいうと、「人口密度を維持する区域」です。
人口密度といっても、基本的な考え方として、人口集中地区(DID):40人/ha以上を保つ区域のことです。*このDIDを維持できなくなってくると人口密度により維持されてきた日常生活に必要な医療、商業系の施設が立地が困難となってきます。
居住誘導区域の役割としては、これから人口減少を迎える地方都市において、人口がまばらのスカスカの都市にならないようにするためです。
イメージしたら分かるかと思いますが、自宅の何軒隣も空き地のある都市って寂しいですよね。
それが、農村部じゃなくて、現在、多くの建築物が立地する市街地といわれる場所で生じる可能性があるんです。
人口密度が低下すると、生活サービス施設の立地が存続が難しくなる可能性が高くなりますし、民間企業にとっても、密度が低いと、経済活動が非効率になります。
(例えば訪問介護であれば、単純に訪問する家の移動距離が今よりも長くなる)
なお、よくある質問で、居住誘導区域外になれば土地の価値が下がっていくんじゃないかという話です。これ対する答えとしては、居住誘導区域外だからといって、すぐに土地の評価が下がるようなことは無いと私は考えています。
>>居住誘導区域外は、土地の評価が下落するの?(ブログ内リンク)
法律上、誘導区域除外義務のある区域
法律では、居住誘導区域から除外する区域について、都市再生特別措置法第81条第19項において、次のように規定されています。
(都市再生特別措置法第81条第19項)
都市再生特別措置法第81条第19項
第二項第二号の居住誘導区域は、立地適正化計画の区域における人口、土地利用及び交通の現状及び将来の見通しを勘案して、良好な居住環境が確保され、公共投資その他の行政運営が効率的に行われるように定めるものとし、都市計画法第7条第1項に規定する市街化調整区域、建築基準法第39条第1項に規定する災害危険区域(同条第2項の規定に基づく条例により住居の用に供する建築物の建築が禁止されているものに限る。)その他政令で定める区域については定めないものとする。
居住誘導区域に定めることができない区域としては、市街化調整区域、災害危険区域(条例により居住系の用途を制限している区域)、政令で定める区域(都市再生特別措置法施行令第30条→都市計画法施行令第8条第2項)が規定されています。
上記のほか、都市計画運用指針(都市計画や立地適正化計画の運用等にあたり指針となる国の手引書)においては、その他の災害ハザードエリア(津波や洪水)についても配慮するよう求めていますので、基本的には災害ハザードエリアについては、居住誘導区域に含めてはならないと考えるのが合理的です。
>>参考記事:令和2年に都市再生特別措置法が改正され、都市防災への配慮が明確化しました。
議論の論点
ここからが、今回の記事の本題です。
自治体によって、このハザードエリアの取り扱いがまちまちなんですよね。
どういうことかというと、ある都市では、河川洪水の被害を受ける恐れがある区域を居住誘導区域に含めているが、ある都市では含めていない。といった感じです。
例えば、沿岸都市で考えるとよく分かります。
高知市は、沿岸都市の一つです。
沿岸部に人口が集中している典型的な都市ですね。
この高知市ですが、津波・河川ともに災害を受ける危険性の高いハザードエリアは、居住誘導区域から除外していません。(土砂災害特別警戒区域は居住誘導区域から除外しています)
今後、防災指針の記載義務を受けて、見直しが行われる可能性があります。
こういった、ハザードエリアを居住誘導区域専門家の間では、区域から除くべきだという意見があります。最近では、新聞記事にも取り上げられていました(どこの自治体だったかは不明・・・)。
しかしながら、自治体では、こうした災害ハザードエリアについて簡単に「居住誘導区域」外とすることはできない理由があります。
例えば、高知市は、人口が約34万人もおり、多くの人が人口密度が高く交通が便利が地域に居住していますが、同時にハザードエリアでもあるため、区域外とした場合の影響が大きいからです。
これは、高知市に限らず、沿岸都市や、河川流域に沿って都市計画が行なわれた都市であれば、当然に起こりうる問題だと思います。
そういった多くの人口を有する地域を簡単に区域外としてしまったら、これまで築いてきた市街地を否定することにもなりますし、当然に、市民サービスについても根本から考え直さなければならなくなるため、行政側としては、「居住誘導区域」に含めないとする判断が非常に難しいところだと思います。
また、区域外とすることで、長期的には資産価値が下がるという考えが行政サイドも把握していると考えられるため、個人資産に関わってくるところですから、慎重に判断しているのだと考えられます。
個人的な見解
確かに、専門家(実務経験から言えばやまけんさんの方が専門家かも・・・www)が言うように、ハザードエリアを居住誘導区域外とすることは、生命を守るという観点からは非常に有効ですし、理想的ではあります。
一方で、歴史があり地域で人口が一定程度存在している旧市街地が居住誘導区域外となることでは、そのエリアの跡地利用や、人口移動(移住)にかかる費用が莫大に生じると考えられます。
そのため、旧市街地については、河川整備や津波防護を進めることの方が有効ではないかと考えられます。つまり、旧市街地の人口が多い地域は、区域から除外しない。
私個人としては、短期的な災害危険性の高い、土砂災害特別警戒区域や急傾斜地崩壊危険区域などは、区域から除外すべきだと思いますが、津波や河川洪水エリアについては、人命救助を最優先としながら、インフラの被害を最小限に抑える都市施設の整備に力を入れていくべきではないかと考えています。
ですので、住民や企業による都市内の生産活動への影響を考慮して、区域に含めるか含めないかを検討することが重要と考えています。
都市自体を安全な地域に遷都するという考えもありますが、現在の日本のように、個人所有だらけの都市では非常に難しいのかなと思います。
江戸時代だったら、発展途上に遷都もありえたのかもしれないですね。笑
ただ、私の考えも、一つ問題があります。
岩手県釜石市を知っているでしょうか、釜石市は、東日本大震災以前から津波による被害を幾度も受けてきては、復興するという歴史を辿ってきたまちです。
東日本大震災では、その釜石において整備された津波防波堤も脆くも崩れ、多くの人命が失われたことも事実です。
ですので、被害想定によっては、移住も都市計画の手法としてあるべきものだとも思います・・・
居住誘導区域についての補足
居住誘導区域は、居住の誘導というように、強制的に誘導するものではなく、国も言っていますが、緩やかな誘導です。
行政手続きとしては、誘導区域外で一定規模の開発行為を行う際に、届出が必要となるくらいです。
ですが、この居住誘導区域について、居住者の方が敏感になることも分かります。
これまでの都市計画の手法が規制的側面のイメージが強かったため、”誘導”という、マネジメント手法の一つが都市計画で語られたということに一種の危機感的要素を多く含む部分だけが表に出てしまったことにっより、”行政から見捨てられる土地”としてのイメージが付いてしまったのかなと考えられます。
人口が一定程度いる現代で、敏感になるのは分かりますが、あと20年したらきっと考えは変わっているはずです。
逆に、20年後に、何故うちのまちは、もっと頑張って居住誘導していかなったんだって言われるところが多く出てくると思います。
私の個人的な考えですが、きっと、そうなると信じています。
ただし、移民政策次第でしょうか。
ちょっと、脱線しますが、移民政策によっては、人口が増える地域も出てくる可能性があります。
だからといって、治安問題を理由として、移民者をある一定の地区にまとめるような施策は絶対によくありません、共存するのが一番です。軋轢を生みます。
まとめ
今回は、居住誘導に関する記事としました。
「立地適正化計画」は、都市計画法に次いで非常に大切な都市居住に欠かせない制度です。
今の私たち市民がもっと注視すべきものだと思います。
最後までお読み頂きありがとうございました。٩( ‘ω’ )و
今後も、まちづくりに関する記事をアップしていきたいと考えていますので、当ブログをよろしくお願いします。


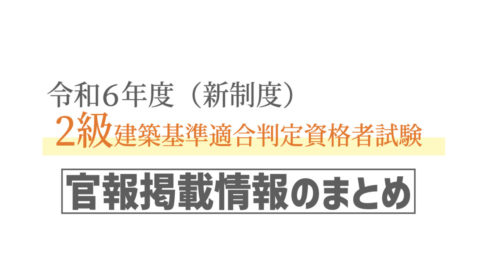
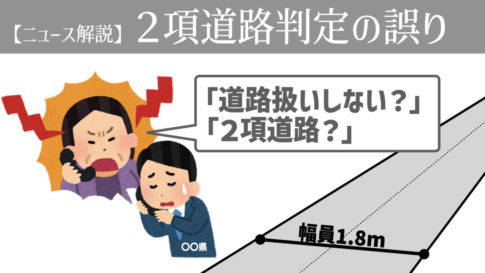
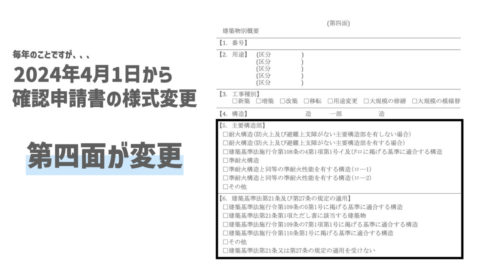


市街化調整区域、災害危険区域(居住機能に限る)、農用地区域、農地、採草放牧地、特別地域(自然公園)、保安林、原生自然環境保全地域等
注)令和3年10月1日からは、上記の区域に加えて、急傾斜地崩壊危険区域、地すべり防止区域、土砂災害特別警戒区域が追加されます。
>>詳しい解説はこちら:https://blog-architect.me/2020/10/22/compact-city-4/