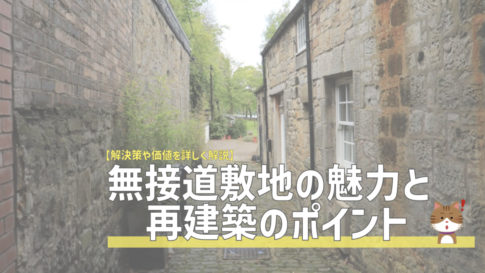なんと言っても、不動産調査において重要なのが建築基準法です。
建築基準法だから建築士に聞かないといけないのか??と思っている方もいるでしょうが、そうではありませんので、この記事を読んで、土地取引の必須知識(私の独断と偏見ですが☺︎)を紹介していきます。
こんにちは!建築士&宅建士のやまけんです。
これまでの建築や都市計画に関する業務経験を活かして建築士や不動産関係者に役立つ情報を発信しています。建築士として、これまでに不動産業者の方から多くの相談を受けていましたので、この記事に訪問された方の悩み解決にきっとつながるはずです。
この記事を読んで、宅建士ビギナーから中級者に成長しましょう!!
では、早速説明していきます。
第5位:地区計画
地区計画は『建築基準法第68条の2』に規定されています。
はじめに、地区計画ついては最も留意するべきポイントがあります。
それは、建築基準法の規定に基づき市町村が条例化することが可能であるということ!つまり、建築基準法が適用されます。よく地区計画は都市計画課やまちづくり課などの都市計画法を所管する部署だけに確認しておけばOKと勘違いされる方がいますが、そうではありません。
通常、地区計画は都市計画法に基づき都市計画決定されます。
都市計画決定されると基本的には都市計画法に基づく『届出』が必要となります。これについては、宅建士を合格された方であればご存知だと思います。
ところが、この『届出』が不要となるケースがあります。それが、建築基準法第68条の2です。
地区計画の条例化によって、建築物の用途をはじめ、建築物の敷地、構造等に関して市町村の条例において制限を定めることが可能となっています。また罰則規定もあわせて定められます。
地区計画だからという理由で都市計画法だけと考えていると後々に取引上のトラブルにつながることがありますから、必ず建築基準法に基づく条例化がされていないか確認するようにしましょう。
- 地区計画は都市計画法に基づき都市計画決定されるが、そのうち建築基準法に基づく条例化される地区計画もある
- 条例化される地区計画については建築基準関係規定となるため、届出よりも法的拘束力を有することとなる
詳しくはこちらの記事で解説していきます。
第4位:建築協定
建築協定は『建築基準法第4章』です。
建築協定は、建築基準法第69条から法第77条までに規定されています。
建築協定のポイントは、住民の任意協定であるということ。
その任意協定を建築基準法での妥当性(法第70条第2項)をチェックした上で、特定行政庁(役所)の認可を受けるものの、運営自体は運営委員会である地域住民に委ねられているため、行政が関与することはほぼありません。
そのため、しっかりと運営を行っているところもあれば、ほぼ機能していない地域もあります。
宅建士としては取引する土地について、『建築協定』がある事実を知り、どの組織で運営されているのか、また、その運営内容について確認しておくだけでOKですが、可能であれば、運営の実態なども調べておくと、将来、運営等に関してお手伝い(ビジネス)することが可能となるかもしれません。
地区計画同様に地域に根差したきめ細やかな制限が設けられているため、売買後に知らなかったと言われていトラブルにならないためにも、事前に内容を確認し、購入者に確実に伝えることが必要です。
- 建築協定は住民等による任意協定であり特定行政庁(行政)が認可する
- 運営は協定に定められた地域組織が行う
第3位:用途地域
用途地域は『建築基準法第48条』に規定されています。
宅建士としてはじめに覚える都市計画法・建築基準法の制限というと用途地域ですね。法第48条に規定されていますが、別表を確認することで、どのような建築物が建築できるか・建築できないかを確認することができますが、この別表を正しく読むことは初心者には難しいはずです。
私が言えることは、勉強しましょう。それだけです☺︎
この用途地域ですが、都市をコントロールするための手法として、基本中の基本となる基礎知識です。申し訳ない話・・・用途地域を説明できない時点で宅建士失格です。土地取引する資格はありません(笑)
よく用途地域は建築士に確認しないとダメなんだ的なことを言うこともいますが、「いやいや、宅建士の試験に出題されているよね」。この用途地域にはこうした用途の建築物は建築できる(できない)と明確に説明できない場合は、恥じることです。
しっかりと勉強して覚えましょう!
これについては、何度も取引を経験するしか確実に覚える方法はありません。数をこなすだけで覚えますから頑張ろう!そして、宅建士としてクライアントからありがとうと言われる本当のプロになろう。
なお、私からのアドバイスとしては、用途地域ごとに『建築することができる建築物』と『建築してはならない建築物』とのに区分されていることを覚えることも重要です。
参考に関連記事を貼っておきます。
第2位:道路
道路は『建築基準法第42条』です。
建築基準法は道路で始まり、道路で終わると言われるくらいに重要です。
建築基準法上の『道路』であるかどうかは、建築物を建築することができるかどうかにかかっています。
不動産調査の基本は道路です。
道路を理解できないと取引もできないですし、道路に関係する容積率・建蔽率の規定も理解することは到底難しいと思った方が良いです。
この規定ですが、業界人では無い一般の方にはわかりません。多分説明しても「??」になるだけかなと思います。道路があってもなくても建築できるものと考えています。
ですから、宅建士であるあなたが一般の方に分かりやすく伝えなければなりません。
では何故、建築基準法上の道路というものが規定されるのか。
最も大きな視点しては防火や避難の観点です。
緊急車両が通行できない道路が出来てしまうと、その狭隘な道路に面して居住している方の生命と財産を守ることが出来無い可能性が大きくなることが理由です。
だから、道路は原則として4m以上と規定されているんです。
実際の実務上、4m道路って狭いです。道路は少なくとも6m以上は必要だなと思うことがあります。なお、4m以上6m未満の私道に接道する場合は、道路位置指定や開発行為による道路の可能性が高いですが、いわゆる開発逃れで建築した可能性が十分にあるため、街区が綺麗に整っているにも関わらず幅員が6mない場合は気を受けましょう。
関連記事はこちらです。
第1位:接道
最も大切な規定は『接道』です。
法律としての規定は建築基準法第43条に規定されています。
道路とセットで必ず学ぶべき法令です。というか知らないと宅建士としては一発OUTです。
ただ学ぶだけではダメです。この接道の規定ですが、ポイントしては、次の2つです。
- 接道が確保されていない敷地の場合、例外認定・許可規定がある
- 自治体の条例により制限が付加されている
接道していないからと言って、必ずしも絶対に建築出来ないというわけではありません。
特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障が無いと認定・許可する要件が定められていますので、取引する土地が無接道だからと落胆せずに、建築できる可能性を探りましょう。
次に2つ目のポイントですが、接道に関しては、建築物の用途や規模等に応じて必ずしも2mの接道とされているわけではありません。
自治体による制限等により用途や規模等に応じて4m以上としなさいとしているケースがあります。ですから、取引する土地の存する自治体(都道府県及び市町村条例)の制限内容は必ずチェックです。
関連記事を貼っておきます。
本記事のまとめ
それでは今回の記事は以上となります。
改めて、宅建士として押さえておくべき必要な知識(私の考え)は次のようになります。
- 地区計画
- 建築協定
- 用途地域
- 道路
- 接道
宅建士になったばかりや宅建士になるために勉強中の場合には、すぐに覚えることは難しいかもしれません。
しかしながら、この5つの知識については土地取引における必須の知識となりますからなるべく早めに覚えるように努力しましょう。
最後に、上記の5つの他にあと1点だけ抑えておくべきポイントがあります。
+αで必要な知識
このポイントについてもこれからの時代においては特に必要な知識となりますので、もっと知識を深めたいと思う方は是非お読みください!! 昼飯代で習得するのに長い時間を要する知識を得られるのは安いかなと思います☺︎
ということで以上となります。
それでは最後までご覧いただきありがとうございました。