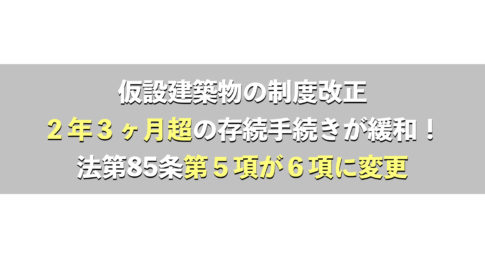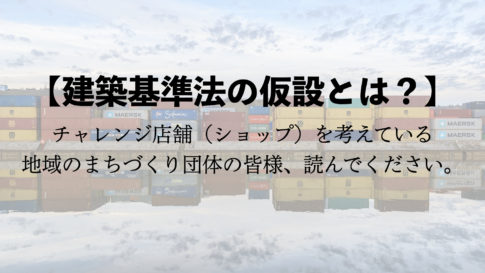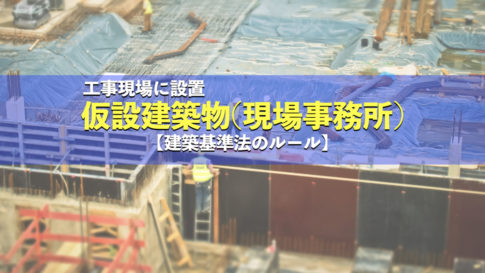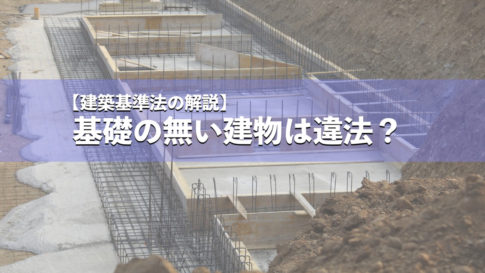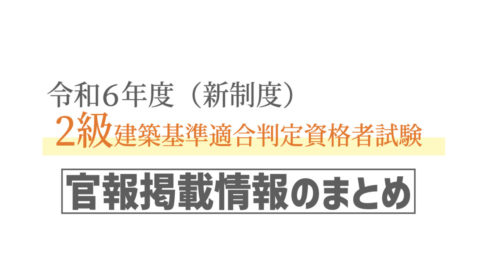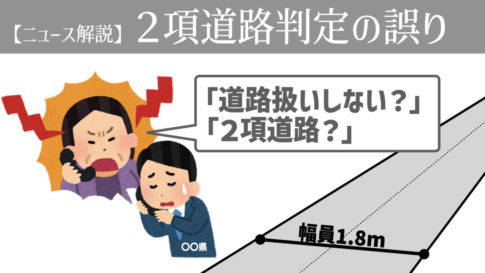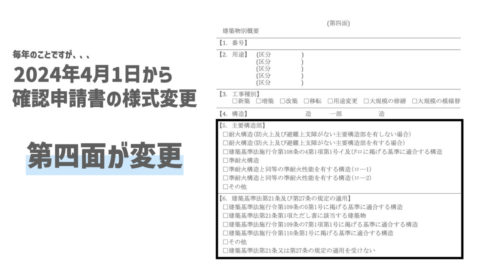はじめに、仮設建築物に対して、「基礎がない建築物だったり、一定期間設置してその後撤去する建築物を仮設建築物というんでしょ?!」という認識を持ったことはないでしょうか?
この記事は、建築基準法における仮設建築物を簡単に理解するための初心者向けガイドです。
仮設建築物とは
仮設建築物は、建築基準法第85条に掲げる建築物に該当する建築物のことで、基礎がないことを持って仮設建築物ということではないです。ここがよく勘違いされてしまうポイントです。
仮設建築物は、非常災害時に建築する一部の建築物を除いて特定行政庁の許可を受ける必要があります。加えて、許可を受けた後は、建築確認申請(1項及び2項の応急仮設建築物を除く)が必要となります。
特定行政庁は、仮設興行場、博覧会建築物、仮設店舗その他これらに類する仮設建築物について安全上、防火上及び衛生上支障がないと認める場合においては、一年以内の期間(建築物の工事を施工するためその工事期間中当該従前の建築物に代えて必要となる仮設店舗その他の仮設建築物については、特定行政庁が当該工事の施工上必要と認める期間)を定めてその建築を許可することができる。この場合においては、第12条第1項から第4項まで、第21条から第27条まで、第31条、第34条第2項、第35条の2、第35条の3及び第37条の規定並びに第3章の規定は、適用しない。
建築基準法第85条第6項(抜粋)
上記法令は、仮設店舗や事務所などを設置する際に許可を取得する規定でして、原則として1年以内の期間を定めて許可されます。許可を受けたあとに確認申請のため、許可手続きに2週間程度、その後の確認申請で1週間〜1ヶ月程度時間を要します。
なお、許可期間ですが、建て替え工事に伴い1年を超えて仮設建築物を設置しなければならない理由がある場合には、その必要な工事期間について許可されます。
空き地に「一時的に仮設のコンテナ(事務所)を設置してもいいんでしょ?」という相談があることがありますが、仮設建築物と認められる建築物は、一時的なイベント用の建築物や工事期間中の代替建築物のみとなります。
注意点
「基礎が無いから仮設建築物」、「一定期間しか設置しないから仮設建築物」というような定義ではないことに注意が必要なのです。一般的に仮設建築物とは建築基準法第85条第6項に掲げる建築物のことをいいます。
注)仮設建築物だから建築基準法は適用されない!というような考えを持ってしまいがちですが、実際は、建築基準法の一部が適用されないのみで、通常の建築物とほとんど変わりありません。
*建築基準法が適用されないものは屋根が無いなどのそもそも建築物には該当しないものをいいます。(参考記事:「建築物の定義」と”土地に定着”の意味とは?)
繰り返しですが、「仮設建築物という建築物の構造や仕様などを定めた定義」があるのではなく、特定行政庁の許可を受けた建築物が建築基準法の一部が適用されないこととなるのみです。
もう少し詳しく仮設建築物について知りたい方はこちらの記事も合わせてお読みください。
関連記事一覧
法第85条改正の話です。
チャレンジショップで仮設建築物を設ける際には違法にならないように注意が必要です。
仮設建築物は開発許可が不要の話です。
現場事務所に設ける仮設事務所の話です。”現場内”をみや誤ると違法になります。
許可後は確認申請が必要になりますよ〜という詳細説明です。
仮設建築物で見落としがちな基礎の話です。
補足:応急仮設建築物について

少し専門的な内容です。
応急仮設建築物については、1項建築物と2項建築物に分かれます。
1項建築物は、特定行政庁が災害発生後すぐに非常災害区域等を指定することであり得る事例ですが、被害が大きかった東日本大震災でも指定は行われていません(行政職員の当時者でしたが、発生直後は救助が優先されます。応急建築を検討するのは救助が完了した後です。)。
1項建築物は、災害が発生した日から1月以内に工事着手するものは建築基準法を適用しないとするもので、国等がつくる救助用の建築物、被災者自らがつくる床面積30㎡以下の建物です。ただし、火災時の類焼を防ぐために防火地域は除かれます。
▶︎1項仮設はそもそも建築基準法を適用しない
2項建築物は、災害時の応急仮設建築物(いわゆる仮設住宅や仮設集会所、仮設店舗など)です。
一般的には地方自治体や独立行政法人(国からの委託)等が災害からの復興を目的として建築します。
1項のような建築主に対する制限はないですが、公益性が求められるため一般的には災害復興計画などで位置付けられています。
建築時は許可不要で3ヶ月を超える前に特定行政庁の延長許可を受ける必要がありますが、建築確認申請は不要です。ちなみに私は東日本大震災時に行政庁の職員として仮設建築物の許可に関わりましたが、その際に多かった相談は「確認申請は必要か?」と「どのタイミングで延長申請すればいいのか?」でした。
なお、2項仮設には工事現場に設ける現場事務所を含まれます。
▶︎2項仮設は一部の規定を適用しない