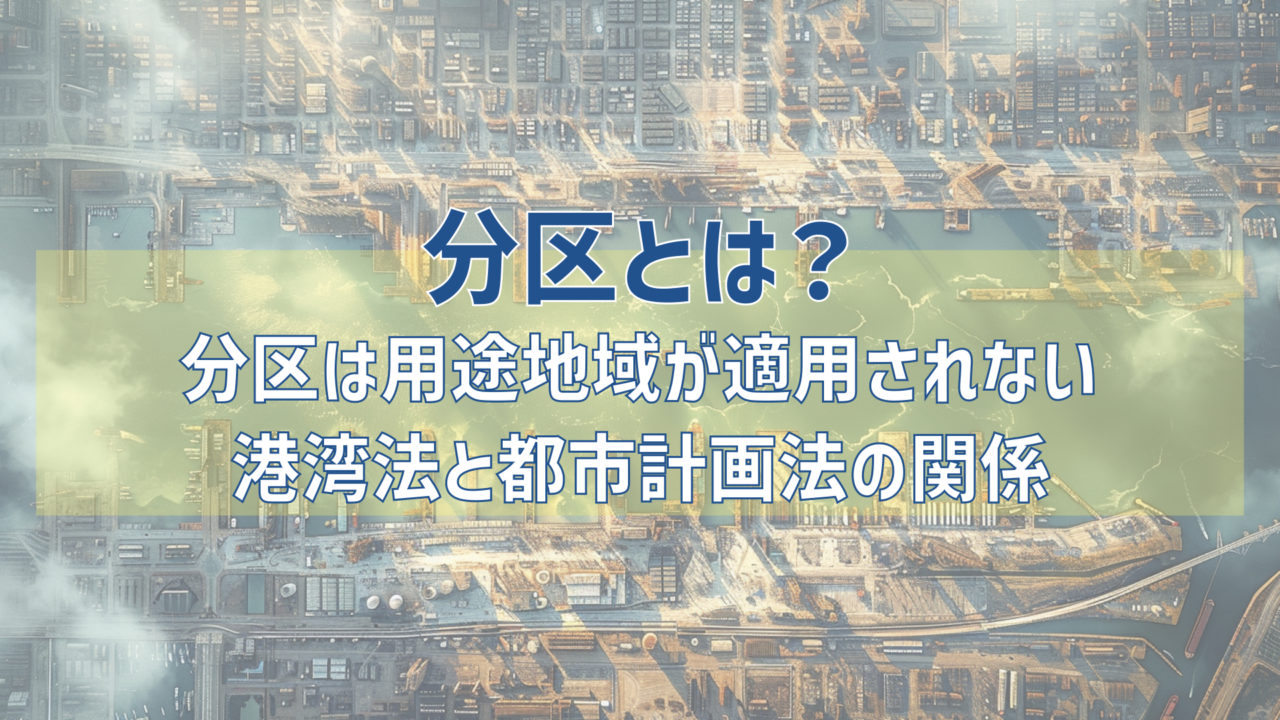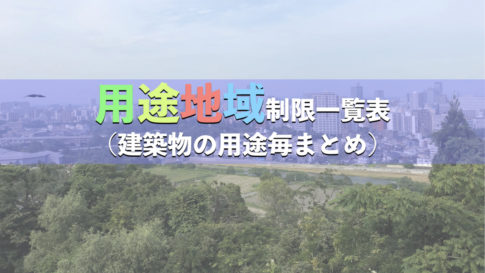臨港地区のうち、分区地区内については用途地域と特別用途地区が適用されない港湾法について触れて解説を行っています。
少しだけニッチな解説になってしまいますが、港湾法と都市計画法・建築基準法の関係は港湾を有する都市での土地取引では重要となります。
こんにちは。YamakenBlogです。
YamakenBlogでは、難解な建築基準法をはじめ、都市計画法や都市再生特別措置法、宅建業法などのまちづくりに欠かすことのできない法律について、出来るだけ分かりやすく解説を行っています。
建築・不動産業界の方々や、これから住宅を建築を予定されている方、店舗経営で立地戦略を検討されている方のお役に立てるはずです。
もし良かったらブックマーク登録をしていただけますと嬉しい限りです。
*こちらサイトリンクはご自由にご自身のブログ内の記事リンクやメール、社内掲示板等で活用頂いてOKです。
用途地域内の建築規制
都市計画区域の中に指定される地域地区(都市計画法第8条)。都市計画法に基づき用途地域が指定されると、建築基準法に基づき、建築物の用途制限が適用されます。
より正しくお伝えすると、都市計画により用途地域や特別用途地区が指定されると、建築基準法第48条(用途地域)と第49条(特別用途地区)により、建物用途の制限が適用されます。ポイントは、建築基準法です。
ですが、臨港地区内で分区が指定されるとその効果が及びません。
その理由について説明していきます。
補足記事:用途地域と特別用途地区
用途地域内の建築制限が除外される法律(港湾法)
この理由については、建築基準法、都市計画法の両法に規定はなく、港湾法に記載されています。港湾法第58条第1項を確認するとわかるようになっています。
建築基準法第48条及び第49条の規定は、第39条の規定により指定された分区については、適用しない。
港湾法第58条第1項
分区??
分区とは、臨港地区内において建築物や工作物の用途等の制限などを行う指定区分のようなもので、港湾管理者が指定する10区分のことをいいます。
つまり、港湾法第39条の規定により指定された分区内については、用途制限と特別用途地区は適用されないのです。
では改めて港湾法を確認しましょ。
港湾法第39条
港湾法第39条により、港湾管理者(都道府県等)は、臨港地区内に分区を指定することができることとされており、分区内においては、港湾法第40条で定める自治体の分区条例で定めるものを建築してはならないとされています。
分区の趣旨としては、港湾機能を阻害する建築物(極端なことを言えば、住宅やマンションなど)を建築させないようにするためです。
用途規制や特別用途地区内の建築制限では、港湾機能に支障をきたすような建築物の用途等を細かく指定することはできないため、分区条例により、規制している港湾都市がほとんどです。
ちなみの分区の種別としては以下のようなものがあります。
分区については港湾計画(港湾管理者が作成)から確認することができます。
- 商工区
旅客又は一般の貨物を取り扱わせることを目的とする区域 - 特殊物資港区
石炭、鉱石その他大量ばら積みを通例とする物資を取り扱わせることを目的とする区域 - 工業港区
工場その他工業用施設を設置させることを目的とする区域 - 鉄道連絡港区
鉄道と鉄道連絡船との連絡を行わせることを目的とする区域 - 漁港区
水産物を取り扱わせ、又は漁船の出漁の準備を行わせることを目的とする区域 - バンカー港区
船舶用燃料の貯蔵及び補給を行わせることを目的とする区域 - 保安港区
爆発物その他の危険物を取り扱わせることを目的とする区域 - マリナー港区
スポーツ又はレクリエーションの用に供するヨット、モーターボートその他の船舶の利便に供することを目的とする区域 - クルーズ港区
専ら観光旅客の利便に供することを目的とする区域 - 修景厚生港区
その景観を整備するとともに、港湾関係者の厚生の増進を図ることを目的とする区域
まとめ・参考書籍
臨港地区内の分区が指定されている区域は、建築基準法第48条及び第49条は適用されないので注意しましょう!対象はあくまでも”分区”であることに注意してください。臨港地区内には分区を定めない”無分区”も多く存在します。
また、港湾法により適用されないのは用途地域と特別用途地区のみのため、他の都市計画である地区計画や防火地域・準防火地域などは適用されます。
≫≫≫参考記事(重要事項説明との関係性)