本記事は、上記の方の悩みを解決するために書いています。
こんにちは。建築士のやまけん(@yama_architect)です。
普段、YamakenBlogでは建築や都市計画、不動産に関して業務に役立つ豆知識を発信しています。試験合格後もこのサイトを有効に使っていただければ嬉しい限りです。
この記事を読みえ終えたあと、”あぁ、こうすればいいんだ!”と思って頂けると思うよう書いていますので、独学で合格を目指したい方は、是非読んでいただければと思います。
>>>独学製図編についてはこちらの記事をご覧ください。
*令和5年版(2023年版)については、設計製図課題が発表されましたら更新する予定ですので、しばらくお待ちください。
目次
本記事を読む前に:受験者への朗報
2022年建築基準法・建築物省エネ法の改正により、現在の予定では、2025年4月(予定)から二級建築士の設計・監理の業務範囲が変わり、従来よりも若干の規模の大きい木造建築物を設計することができるようになり、より活躍しやすくなります。
詳細は、こちらの記事に書いておりますので是非ご覧ください。
無料で勉強できるブログ記事の紹介
建築士試験向けに無料ブログ記事を二つ書いています。
一つ目は、二級建築士学科試験の建築計画に出題される建築物についてです。もう一つは、法規に関する問題で、法令集不要で勉強できる構成にしています。
仕事の合間や通勤中などでご覧いただくと良いのかなーと思います。
>>>建築計画のうち日本・西洋建築物に関する出題
>>>合格するために必要な法規の用語を解説している記事(試験日まで順次更新中です)
はじめに
ではでは前置きが長くなってしまいましてすみません。
ここからが本題です。
実際、実務に携わってみると二級建築士を有していれば、建築に関わる大抵の仕事ができますので、無理せずに一級建築士を取る必要は無いと考えることがあります。
あくまでも民間で資格を使って仕事をすることを前提として話していますので、一級建築士を目指すことを否定しているわけではないのでご理解くださいません。
私自身は、元行政人でしたので一級建築士を取得して建築主事になるまでが公務員の責務と考えていた方なので、一級まで目指しましたが、実務上は2級の知識で十分なことが多いですし、実際、地元で活躍されている建築士の方々は、行政の窓口でも2級の方が多かった印象です。
加えてですが、今後の急速な人口や世帯数の減少するため、それに伴い縮小する国内のマーケットでは、一級建築士が設計するような大規模なものが極端に減少すると考えられていることも理由の一つです。仕事自体が無くなるわけでは無いですが、仕事量自体は減っていくでしょうし、木造推進の社会では大規模木造よりも小中規模木造の方が設計しやすいので、そうなると2級でOKとなる傾向になりそうです。
⬇️に関連記事を貼っておきます。
また、そもそも建築士という仕事や二級建築士の仕事が分からない方はこちらの書籍や記事をご覧ください。当ブログに辿り着いたあなたの悩みを解決してくれるかもしれません。
文系の出身でも二級建築士になれるの〜?という相談を受けることがありますが、わたしの知人女性で文系出身(高卒)から一級建築士になった方もいるので、理系か文系かは気にする必要はないです。やる気と努力量次第で取得可能です。
独学合格は可能
春先頃から二級建築士の勉強を始める方が増えますよね。
今回で絶対に合格するぞっと意気込みに溢れている方、とりあえず受けてみようかなと考えている方、さまざまかと思いますが、受験するからには合格したいですよね。
受験費用が高いと思うか低いと思うかは人それぞれですが・・・。受験手数料はそれになりしますしね。それに合格するには当然ながら勉強が必要です。
2級建築士は一夜漬けでも合格できると言っている方もいますが、わたしもを含め、普通のひとには無理だと思います(泣)
自分の時間を試験勉強に投資するんですから、やっぱり合格したいですよね。加えて、近年は賃金は上昇せず物価高の時代なので、できれば費用をかけずに「独学」で!と考えるはず。
私は現在、一級建築士ですが、二級建築士については、大学を卒業してからすぐに取得しました。
わた氏の場合は「独学」で勉強して合格しています。
そこで、独学で合格するための勉強のコツをお伝えしたいと思います。
これから試験勉強に取り組んでも問題ありませんので、合格したいと考えている方は最後まで是非読んでみてください。
補足:令和2年度から受験資格が緩和
令和2年度の試験から受験資格が緩和されています。(*詳しくはこちら)
改正点としては、建築系高等学校を卒業後すぐに受験できるようになったところがポイントです。
なお、注意点として、受験資格が緩和されただけで、登録要件は変更ありません。よって、試験に合格したとしても登録するための要件に該当しなければ建築士としての仕事はできません。
とはいえ、受験要件が緩和される効果は大きいので、来年度から受験者数は増加するでしょうね!
ちなみですが、学科試験合格後は当該試験年度を含めて5年間は製図試験の受験が可能(4年間は学科免除)です。ですから、これだけ受験者数を増やしたいということは、ほぼ確実に将来的に建築士が不足するんでしょう。
| 受験資格要件 | 免許登録要件(学歴) | 登録免許要件(実務経験年数) |
|---|---|---|
| 0年 ※大学・短期大学・高等専門学校(建築系学校) | 大学・短期大学・高等専門学校(建築系学校) | 無し |
| 0年 ※高等学校・中等教育学校(建築系学校) | 高等学校・中等教育学校(建築系学校) | 2年以上 |
| 実務経験年数7年以上 ※建築系以外の学校 | ー | 7年以上 |
| 都道府県知事が同等と認める者 | 都道府県知事が同等と認める者 | 所定の年数以上 |
二級建築士(学科)の難易度・合格率
二級建築士学科試験の難易度ですが、過去5年間の合格率を見ると約3割から4割で推移しているので、一般的に考えれば難しい試験の部類に入ると思います。
更に学科試験を合格した後は、製図試験があり、最終合格率は約2割程度(2022年の最終合格率は25%)となりますので、そうそう簡単に合格することはできないのが実態ではないかと思います。
特に製図試験に関しては、合格率が約半分ではあるものの、製図試験に挑むためには製図という長時間必要な勉強を行わないといけないという精神的疲労と肉体的疲労が伴い、かつ本試験でエスキスがピッタリとハマらなかった場合の運的なものを考慮するとかなり難しい試験の一つだと思います。
学科の試験問題は100問、試験時間は6時間ですので、勉強する分野も広く、満遍なく勉強しないと合格は難しいと思いますから、建築の知識を有していても一夜漬けで合格点に達成するのは難しいと思います。
ここ近年は、学科試験の合格率は高めに設定されている印象を受けます。
おそらく建築士不足も関係するのかなと想定していますが、過去には30%もあったようなので、この割合を取れば合格するとは思わずに合格するためには『確実に勉強量をこなす』ことが大切だと思います。
ではでは、「確実な勉強量」とは具体的にどうす勉強すればいいのか、私の考えを説明していきたいと思います。いかに楽して合格できるかを焦点としているので参考になれば幸いです。
その前、次の合格基準点をみたあとに詳しく解説していきたいと思います。
学科試験の合格基準点
昨年度の試験である令和4年の学科試験結果を見てみます。
通常、13点が基準となり総得点が60点となります。つまり、13点*4分野=52点となるため、+8点をどこかの分野で得点する必要があります。
なお、令和4年度試験については、法規と構造が若干簡単だったのか14点が基準点となっています。
| 学科Ⅰ 建築計画 | 学科Ⅱ 建築法規 | 学科Ⅲ 建築構造 | 学科Ⅳ 建築施工 | 総得点 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 基準点 | 13点 | 14点 | 14点 | 13点 | 60点 |
各出題項目で約6割以上得点し、合計でも6割以上得点すれば合格することができます。
勉強のポイントとしては、60点ギリギリでの合格ですと合否が気になってしまい製図試験勉強にあまり力が入らないので、ある程度の合格安全圏である70点合格を目指します。
全ての分野において知識がある程度ないと合格するのは難しいと思います。
よく、構造が苦手という方がいますが、構造も基準点を満たしていないと他の項目が基準点を超えていても不合格になりますので、広く浅くでいいと思いますので、ある程度の知識を習得する必要があります。
二級建築士学科試験の出題項目
勉強のコツの前に、出題項目について確認しておきましょう
学科の試験は出題項目が4つ(建築計画、建築法規、建築構造、建築施工)に分かれており、各25問出題され、計100問を午前3時間、午後3時間の計6時間で解くことなります。
ちなみですが、出題の基準は建築士法施行規則第13条に規定されているので、お時間がある方はどうぞ。
- 各種の用途に供する建築物の設計製図及びこれに関する仕様書の作成
- 建築物の用途に応ずる敷地の選定に関すること
- 各種の用途に供する建築物の間取りその他建築物の平面計画に関すること
- 建築物の採光、換気及び照明に関すること
- 簡易な建築設備の概要に関すること
- 各種建築材料の性質、判別及び使用方法に関すること
- 通常の木造の建築物の基礎、軸組、小屋組、床、壁、屋根、造作等各部の構造に関すること
- 簡単な鉄筋コンクリート造、鉄骨造、れん瓦造、石造又はコンクリートブロック造の建築物の構法の原理の概要並びにこれらの建築物の各部の構造に関すること
- 建築物の防腐、防火、耐震、耐風構法に関すること
- 普通のトラスの解法、簡単なラーメンに生ずる応力の概要又は普通のはり、柱等の部材の断面の決定に関すること
- 建築工事現場の管理(工事現場の災害防止を含む。)に関すること
- 建築工事の請負契約書、工費見積書又は工程表に関すること
- 普通に使用される建築工事用機械器具の種類及び性能に関すること
- 建築物各部の施工の指導監督及び検査に関すること
- 建築物の敷地の平面測量又は高低測量に関すること
- 法及び建築基準法並びにこれらの関係法令に関すること
では、ここからが今回の記事の本題です。
楽に合格するための試験勉強のコツ
結論としては、『過去問を解く』です。
というのは、テキストを読みつつ過去問を解いていくと、テキストで勉強する時間のコストがかかるために結構大変です。
ですので、2級建築士の学科試験であれば、過去問を解きつつ、分からないところはテキストやインターネットで検索して覚えれば十分に合格点に到達すると思います。
その上で試験勉強は、過去問をひたすら解く分野とそうではない分野に別れていると考えています。括りとしては、『計画・構造・施工』と『法規』です。
では、どういうことか詳しく解説します。
建築計画・建築構造・建築施工の勉強のコツ
建築計画・建築構造・建築施工は、建築基準法の法文と直接関係する問題は、少ないと言っていいです。
実務的な設計に関してのことだったり、建築歴史に関する分野、一般的な建築施工に関しての知識を問う問題が出題されます。
つまり、過去に出題された問題が頻繁に出題されることを意味します。
これらの問題の分野は、社会的にこれまでの数年間の間に建築設計のあり方が大きく変わったわけではないです。ですので、新たな問題を頻繁につくって出題するというのは難しいので、出題傾向は大きく変わらない分野になります。
ですから、結果として、過去に出題された問題を問き、分からない部分を市販のテキストや大学の教科書を見ながら勉強していけばいいわけです。
よって、過去問→テキストをチェック のループをひたすらやり続ける事が秘訣です。
少なくても過去5カ年分を3回は解くようにするのが楽に合格すためのコツです。
- 100問*5ヵ年*3回=1,500問
- 1問あたりの勉強時間が平均して10分とすれば、15000分=250時間が必要
- 1日5時間勉強すれば、50日で完了することができます。
とはいえ、5年間分を勉強するのは時間的に厳しいと思いますので、
難しい場合は、3カ年分であればなんとかなるかもしれません。
- とにかく過去問を解く。
- 過去問は少なくとも過去3ヵ年分を3回以上解く。
おすすめ書籍(計画・構造・施工)
過去問を解くため、過去問題集があれば合格は可能と考えられます。
とはいえ、建築施工に関しては、用語の意味をある程度理解できないと「文字」だけ覚えるという最悪な状況に陥る可能性もあるので、それは避けるべきです。そのためにも、建築施工の用語を調べることができる参考書や当サイト、Google検索がおすすめです。
テキストに関しては、総合資格学院と日建学院のどちらか一方を使えば十分です。
お金が無い学生は、過去問だけ買いましょう。
私自身も下記の過去問だけを購入してひたすら勉強していました!!
>>基本的な勉強としては、過去問題集のみ使用します。
※過去問は大手2社のどちらを選択してもOKですが、建築資料研究社の方が若干安いです。
>>建築用語等に不慣れの方は図解で理解することも大切ですのでイラスト系で教えてくれる書籍を購入するようにしましょう。
電車などの移動中に読めるKindle版は勉強時間を効率よく確保できます。
建築施工で出題される用語を覚えるには図解を見た方が効率が良いので、おすすめです。
では、次に建築法規の勉強のコツです。
建築法規の勉強のコツ
現に私も受験した時は法規に慣れていなかったので、法令集も引くのも大変だったですし、法律の読み方まで覚える必要があるので、言い回しを含めて何を言わんとしているのか学習するのに苦労が絶えなかったです(汗)
では、どうすればいいか・・・
方法は、計画や構造、施工とは異なり、過去問ではなくテキストの勉強をメインにすることです。
テキストを読みながら法令集を見ていく作業を行います。そうすると法令集の中で出題される法文の条文が分かってくると思います。
テキストを読みながら過去問を解き法令集を用いて勉強する工程は一見して大変そうだし、時間がかかりそうなイメージですが、法規の問題は法令集に答えが書いてある唯一の分野です。この法規をマスターしてしまえば、他の分野が足を引っ張っても合格点まで引き上げてくれます。
繰り返し勉強して「○条にはこういった事が規定されているのか」と分かるようになってくればOKです。テキストを読みながら法令集を見る作業を繰り返し行ったら、次は、過去問を解きましょう。
建築計画などと同様に過去3カ年分は3回解いておくのがいいです。
ちなみにですが、法規の問題は、法令集に答えが掲載されているので、素早く法令集を引けるようになり、書いてある内容を理解できるようになれば満点も取ることも容易です。
これは私の個人的な見解ですが、法規は実際の実務で多く使用するものですので、試験勉強を活用して法律を理解しておくことは実務側と連携が図れます。
また、法規で満点を取れるようにしておけば、他の項目で点数が低くても合格できるようになるので、法規を優先して勉強しておくのが良いのかなと思います。
- テキストを解く(どこにどのような法文が掲載されているか理解する←ここがめっちゃ重要です)
- 次に過去問を解く。
- 過去問は少なくとも過去3ヵ年分を3回以上解く。
>>法令集の使い方に慣れていない方はこちらの記事もあわせて読んでみてください。
法規試験:おすすめ書籍私は普段の業務でもこちらの法令集を活用しています。様々な法令集を使いましたが、私自身は一番使いやすいと考えています。
私の感覚的なところもありますが、こちらの法令集を使用している行政庁の方は多いという印象ですので、実際の実務の方が十分に効力を発揮すると考えられます。
ちなみにインデックスは付けません。つけるとダサいですしほんとで不要です。インデックスつけている暇があるのであれば、勉強しましょう。
▽下記の法令集ですが、例年1月下旬に販売されます。わたしはずっと愛用している法令集ですのでおすすめです。
法規の勉強に関する過去問やテキストは、建築計画や構造などと同じものでOKです。
>>>これから2級建築士試験の勉強方法をなどを解説したnoteを作成しました。
購入特典として建築法規に関する無料質問(5問)をセットにしていますので、勉強していて分からないことがあるなど、独学で悩んでいる方はぜひ活用ください!!
本記事のまとめ
今回、解説した勉強方法については、過去問を活用した勉強方法は出題範囲と出題される内容の趣旨を理解できるので、効率が良い勉強方法になりますから、限りある時間の中で合格を目指す方は、今回紹介した勉強方法を参考にしてみてはいかがでしょうか。
>>>未経験から建築士・宅建士になるための方法など書いた記事もあります。
>>>宅建士試験を受験される方は是非こちらの記事もお読みください。
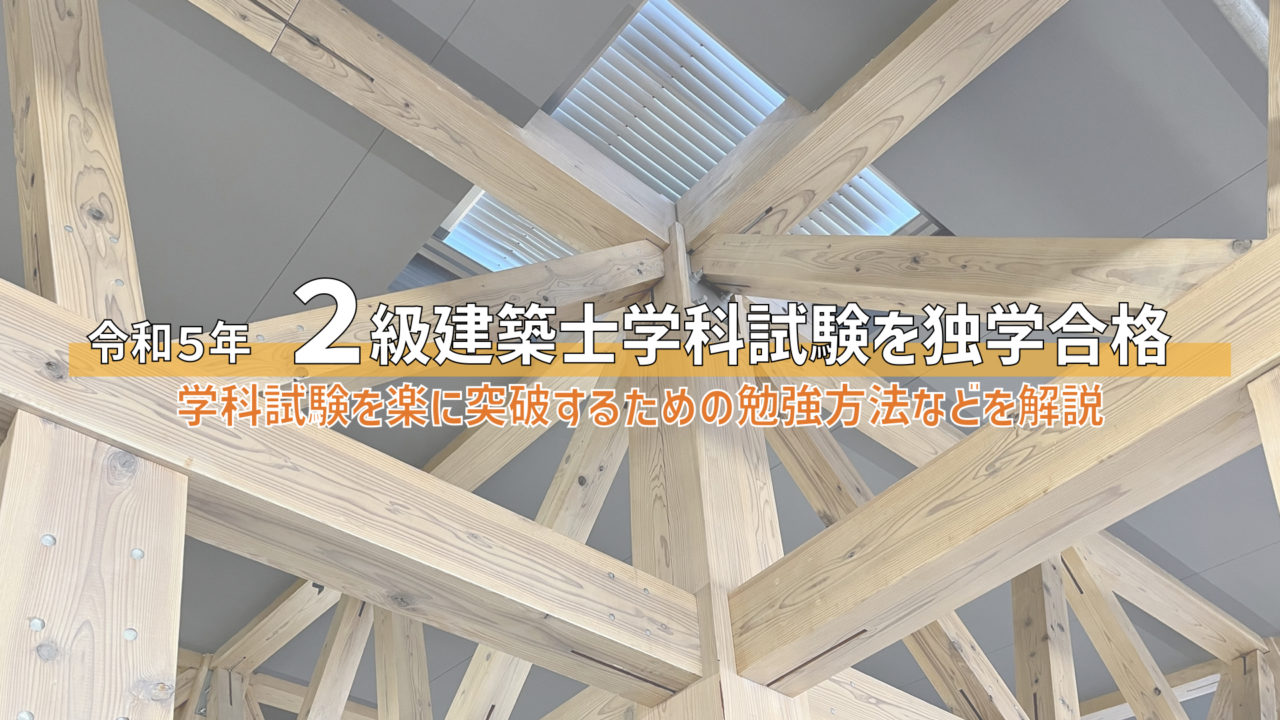
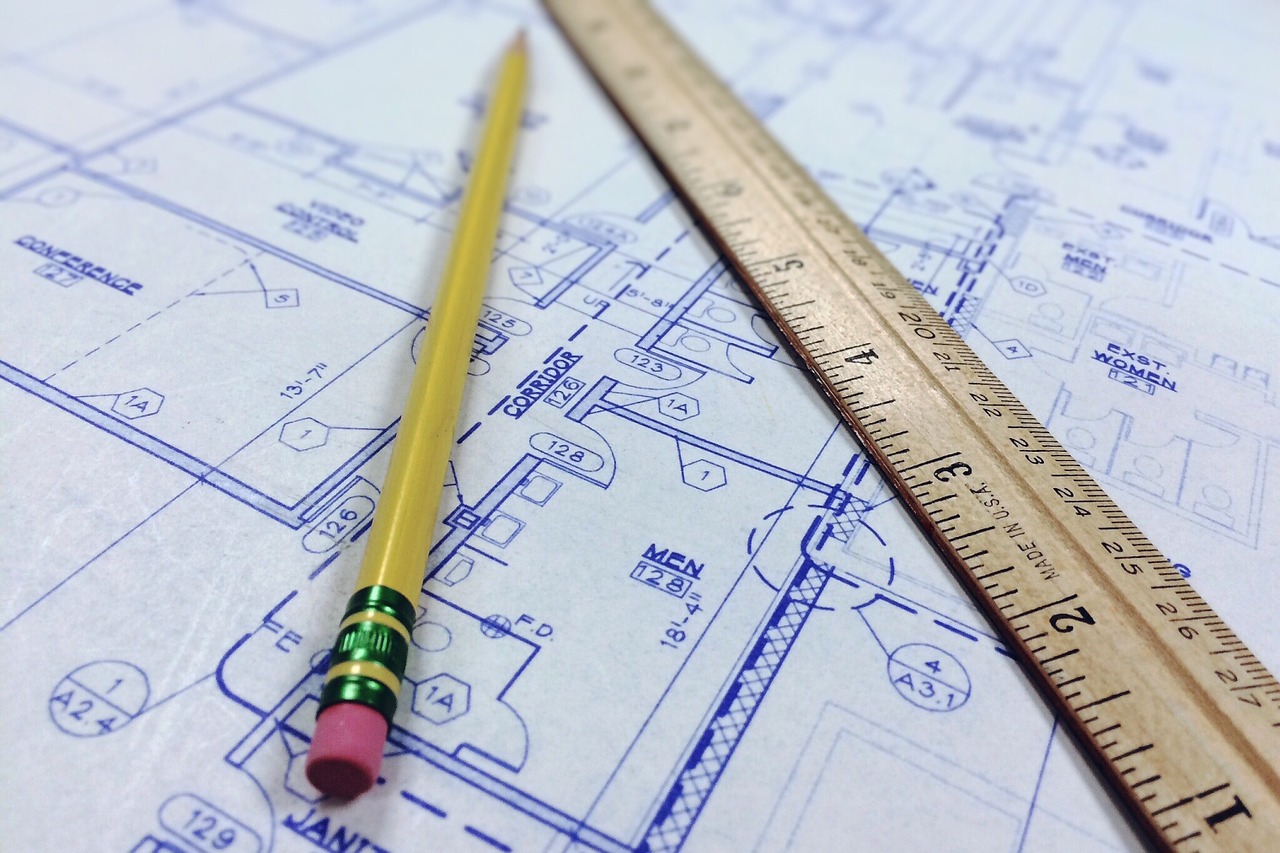
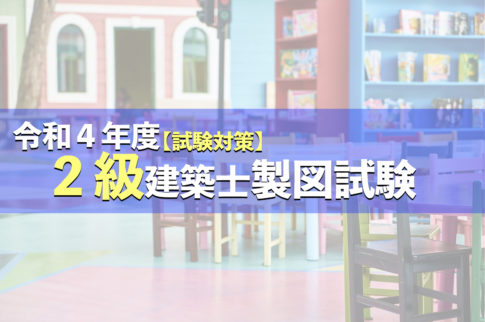
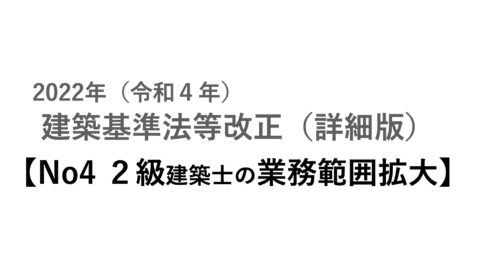

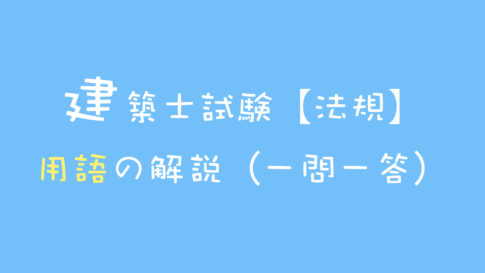


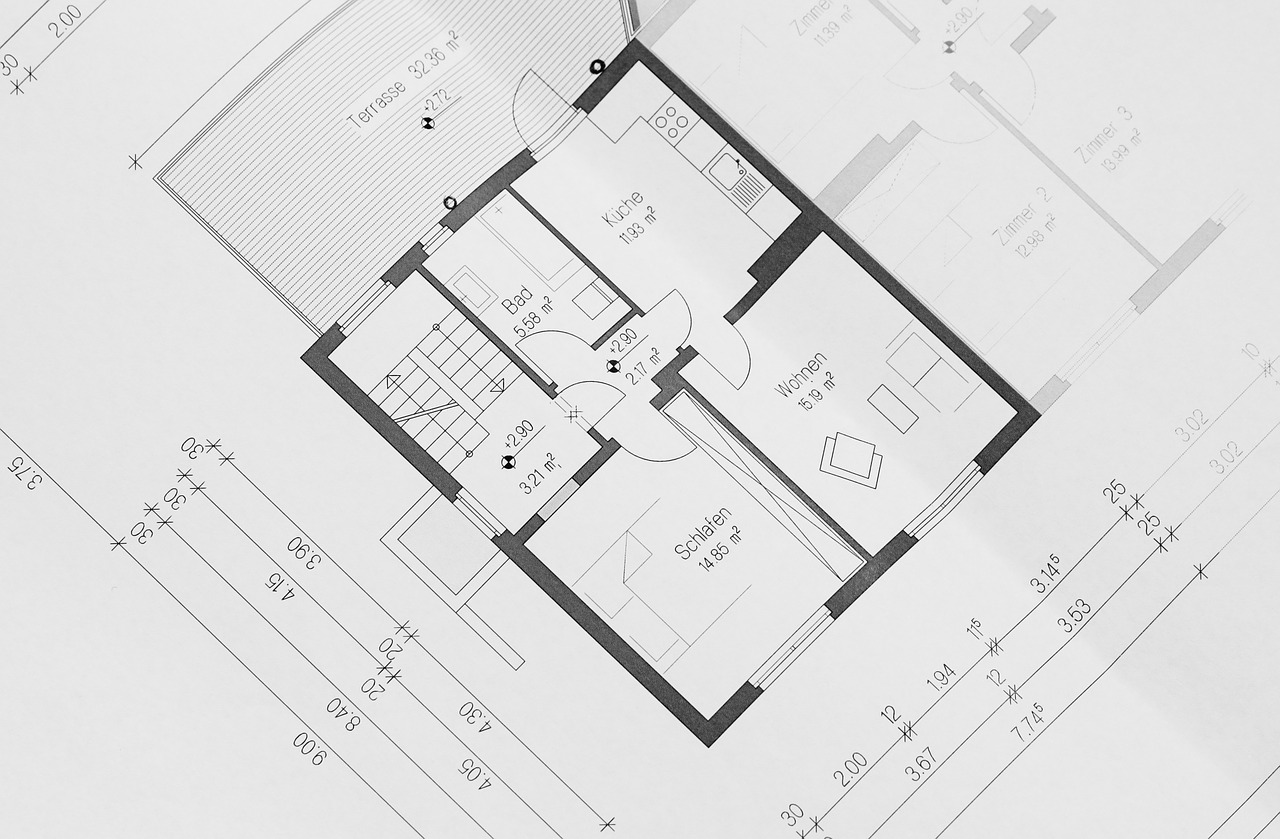





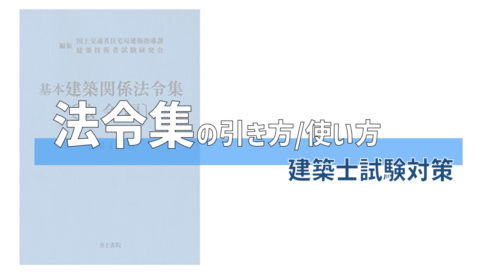



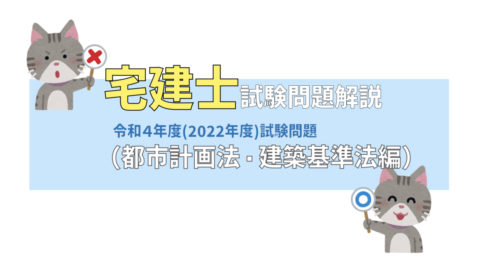





※出典:公益社団法人建築教育技術普及センター